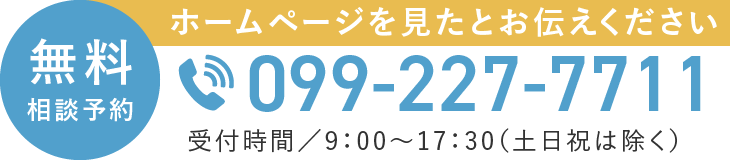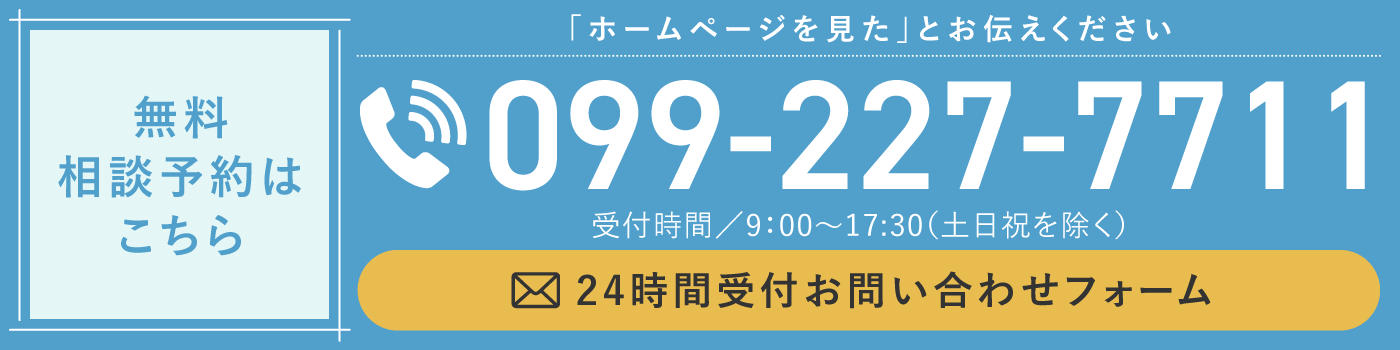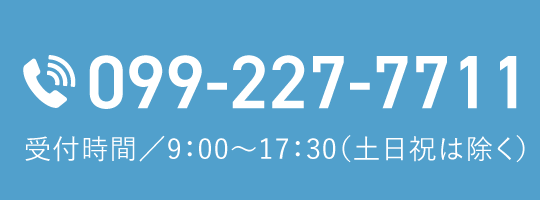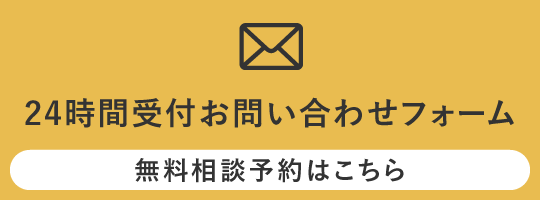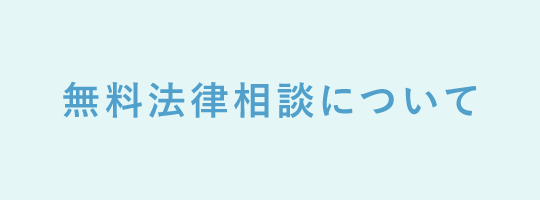1 はじめに
前回と同様、今回も、後遺障害申請についてお話します。
おさらいですが、交通事故の被害者の方が、後遺障害の申請に当たっては、相当程度の通院を継続し、症状固定となった後に、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。その後、調査事務所で判断がなされます。
労災の場合と異なり、一部を除いて面談等が実施されることはありませんので、交通事故の場合には、この後遺障害診断書の内容が重要であることは、このコラムの中でも何度もお伝えしてきました。
2 可動域制限
交通事故の被害に遭われた方の中でも、むちうちと並んで多く見受けるのが、整形外科領域の可動域制限です。
特に骨折された方の場合、この可動域制限が一番と言っていいほど問題となると思います。
さて、この可動域制限ですが、正常値と比較して、どの程度、可動域が制限されたのか、多動値ないし自動値という数値を基に評価されます。
自動値は、対象者が、自力で関節を動かした場合の可動域のことをいいます。
他動値は、他人(主治医など)が、手を添えて関節を動かした場合のことを言います。
関節可動域の測定について、自動値と他動値の違いは、要は、自力で動かすか他人が動かすかという違いになります。
そして、関節可動域の測定は、後遺障害診断をするにあたっては、原則として他動値で判断することになります。
どのくらい可動域が制限されると何級と評価されるのかは、以下のページで明記しています。
4分の1制限されると12級
2分の1制限されると10級
というのが割合としては多い印象です。
3 測定方法
以上は、これまでの基礎知識をまとめました。
本日は、この後遺障害診断書を作成してもらうに当たって、注意が必要なケースを紹介します。
これまでお読みいただいた方には分かると思いますが、重要なのは後遺障害診断書にどのような数値が記載されているかです。
測定方法等が問題となります。
他動値の測り方について、測定する医師によっても、どこまで力を入れて測るかといった違いはあると思います。
それよりも重要なのは、どのようなシチュエーションで測るかです。
もちろん、これは、日常生活において、どの程度、可動域が制限されているかを測るものであるため、リハビリ治療等を受けていない、いわば「素」の状態の可動域が測られていなければなりません。
しかし、中には、リハビリ治療を受けた直後に、可動域の測定がされているケースもあります。これですと、交通事故の被害に遭われた方は、リハビリを受けて、筋肉の硬さもほぐれている状態で測定されていることになりますから、「素」の状態よりも可動域制限は緩和されている状態であると思います。
後遺障害の認定がなされるか、あるいは、より上位の認定がなされるか微妙なケースでは、このように、どのようなシチュエーションで測定されているかによって結論が変わってくる可能性があります。
最近、当事務所で依頼を受けたケースでは、上記のようにリハビリを受けた後に測定されていることから、「素」の状態より良い検査数値が出ていました。しかし、打ち合わせて事情をお聞きしたら、本来はもっと状態は悪いということでしたので、再度、リハビリをする前の状態で検査をしてもらいました。
おそらく、当初の検査数値では、後遺障害は認定されなかったのではないか、あるいは12級ではなく、神経症状として14級が認定されていたのではないかと思います。
4 まとめ
このように、交通事故の被害者の方が、適切な後遺障害の認定を受けるためには、相手方保険会社からの指示に従って主治医に診断書を作成してもらうだけでは不十分です。
特に可動域制限であれば、どのような測定方法で、どのような数値が出ているのか、あるいは、その可動域制限が生じた原因は何かまで掘り下げて検討する必要があります。
後遺障害の申請には、弁護士のアドバイスが重要です。
お困りの方は、是非、経験豊富な上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。