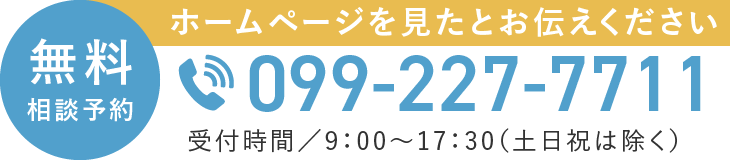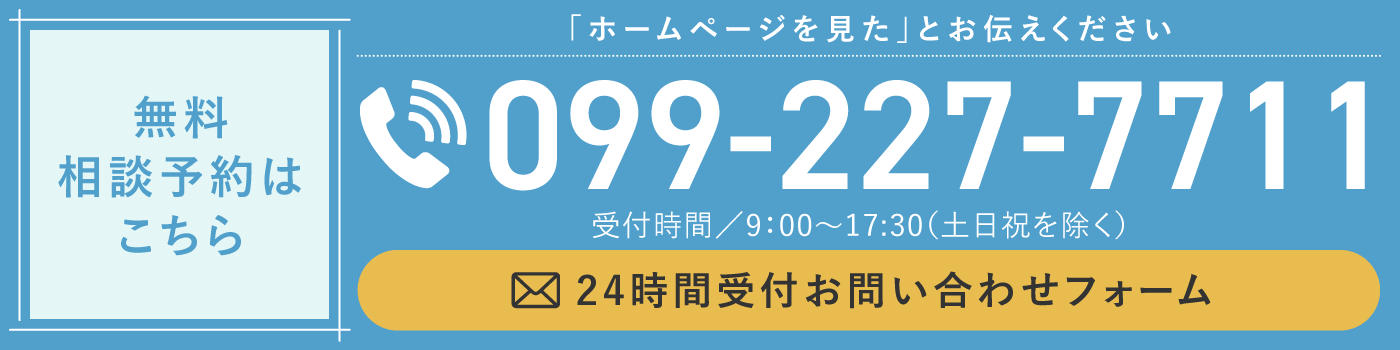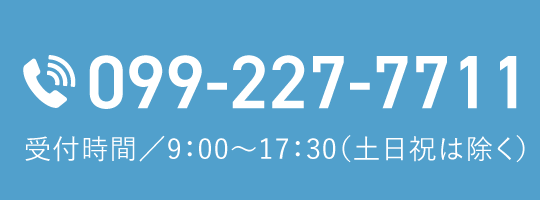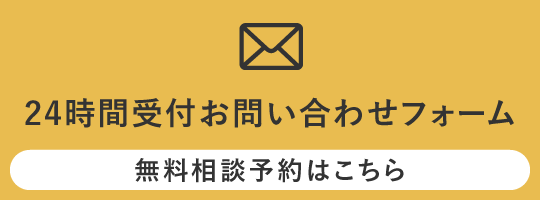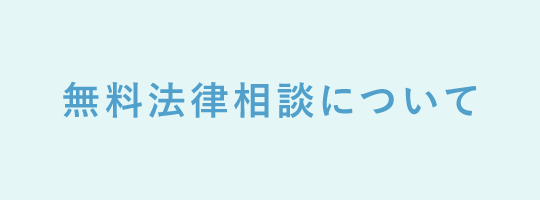Archive for the ‘交通事故の治療について’ Category
交通事故と介護保険
1 はじめに(交通事故と介護保険)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
治療費と健康保険の関係については、前回のコラムで記載した通りです。
では、介護保険はどうなるでしょうか。
2 介護保険の場合
過失割合が0対100の事故の場合に、どうして被害者の側が手続きを取らないといけないのかと思われるかもしれません。
平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
鹿児島市のHPも引用しておきます。
介護保険制度では、介護サービスを利用する際、被保険者は利用料の1割~3割を負担し、残りの9割~7割を保険者(自治体)が介護保険給付として負担しています。
交通事故など第三者(加害者)が原因で介護が必要になった、もしくは要介護状態が悪化した場合は、被保険者(被害者)が介護サービスを利用する際にかかる費用を、原則第三者(加害者)が負担することとなります。
この場合、被保険者の介護サービス利用負担分(1割~3割)については被保険者自身で第三者へ請求し、残りの介護給付分(9割~7割)については被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得して、保険者が過失割合に応じて第三者へ請求することとなります。
つまり、最終的には、加害者が負担することになるのは変わりありません。
3 まとめ
以上のとおり、介護保険を利用する場合に、所定の手続が必要になります。
ただ、過失割合の問題もある場合には、健康保険と同様の問題がありますし、基本的には介護サービスを利用する必要がある場合には、所定の手続をとって利用すべきです。
上山法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
治療費をどうするか
1 はじめに(治療費をどうするか)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
通常、被害者側の過失が大きいといった事情が無い場合には、保険会社が治療費を病院に支払う運用がなされています。
これをそのまま、気にすることなく続けてよいのでしょうか。
2 労災の場合
労災の場合、治療費は労災から出ます。
休業損害について、特別支給金が出ることから、労災に該当する場合には、労災を積極的に利用した方がいいと思います(これは、損益相殺として差し引きされません)。
では、労災以外の場合にはどうでしょうか。
基本的には、被害者側に過失がない場合には、特に気にする必要がないかなと思います。
ただし、自賠責保険の傷害部分の上限金額は120万円であり、加害者側の保険会社は、治療費等含めて被害者に支払う損害賠償金の総額が120万円を超えそうになると、保険会社の自腹分が出ることを避けるために、治療の打ち切りや治療費の支払いの打ち切りを宣告することがあります。
通院が頻回で、120万円の枠内を治療費が多く占めてしまうような場合、結果として、慰謝料が圧縮される格好になる可能性もあります。
健康保険に切り替えれば、結果として慰謝料を確保した示談がスムーズになる可能性はあります。
また、被害者側に過失がある場合はどうでしょうか。
被害者にも過失がある場合には、被害者も、自身の過失の限度で治療費を負担することになります。
健康保険を利用しないことにより治療費が膨れ上がれば、被害者の負担も大きくなります。
例えば、被害者の全損害が1000万円、過失割合が加害者80%、被害者が20%とすれば、被害者が受け取れる損害額は800万円になります。
このとき被害者が健康保険を使わず自由診療を受け、その治療費が100万円とすれば、被害者が受け取れる800万円を治療費の支払に充てると、被害者の手元には700万円が残ります。
しかし、健康保険を利用すれば、自己負担分は3割の30万円ですので、800万円―30万円=770万円が被害者の手元に残ることになります。
したがって、被害者にも過失がある場合には、健康保険を利用した方が被害者に有利になるのです。
3 まとめ
以上のとおり、治療を継続する過程でも気を付けないといけないことがあります。
上山法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。。
逸失利益についてのおさらい② 未就労年少者の後遺障害逸失利益の場合
1 はじめに(逸失利益についてのおさらい② 未就労年少者の場合)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
交通事故の被害に遭われた方が亡くなってしまったり、後遺障害が残存したりした場合、逸失利益が問題となります。
逸失利益とは、その被害者において事故がなければ得られたはずの将来の利益のことをいいます。 逸失利益は、基本的には将来の収入を現在に割り戻して算出します。
これまで、本サイトのページやコラムでも、以下の通り、たくさん投稿してきています。
今回はは、未就労年少者の逸失利益についておさらいしたいと思います。
【後遺障害の逸失利益】
【高齢者の逸失利益(年金)について】
【逸失利益のおさらい①】
2 未就労年少者の後遺障害逸失利益
後遺障害の逸失利益は、原則として、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。
未就労年少者の場合、「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」が、症状固定時から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数から、症状固定時から就労開始までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引いたライプニッツ係数を乗じて算定します。
「基礎収入」について、 年少男子の場合、原則として、男性労働者の全年齢平均賃金(以下「平均賃金」といいます)を基礎とします。
年少女子の場合、男女を合わせた全労働者(以下「全労働者」といいます)の平均賃金を基礎とします。
医学部、看護学部、薬学部等で専門教育を受けている学生については、特定の職業に就く蓋然性が認められる場合、職種別の平均賃金を基礎とします。
また、大学生等又は大学等への進学の蓋然性が認められる場合、大学卒等の平均賃金を基礎とすることもあります。
しかし、これには注意が必要です。年少者の基礎収入を大学卒の平均賃金とした場合には、就労開始の時点が変わります。高校卒であれば18歳からになりますが、大学卒だと22歳からになります。そのため、大学卒の方が、平均賃金が高いから有利になるかというと、単純にそうではありません。
この点は間違いが起きやすいので、しっかりとシュミレーションをしてから検討すべきです。
3 まとめ
以上のとおり、未就労年少者の後遺障害の逸失利益について述べてきました。
基礎収入について、職種別や大学卒で検討すべきかは、よく考える必要があります。計算もきちんと専門家に行ってもらい、正確な金額を算出してもらった方が安心です。
上山法律事務所では、後遺障害事案も多く対応していますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
症状固定後の治療費
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方が保険会社に加入していれば、原則としては、相手方の保険会社が治療費を直接、医療機関に支払うという扱いになることが多いと思います。
一定期間、治療を継続し、症状固定になれば、示談交渉が始まります。
この一定期間については、事故態様や傷害の程度により様々ですが、むちうちの場合は長くて6カ月程度、整形外科領域で骨折があると6か月から1年程度、頭部外傷だと1年から1年半くらいというのが、大まかな整理です(本当に大まかではあります)。
症状固定とは、「怪我の治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない」という状態のことですが、基本的には主治医のアドバイスに従ってタイミング等を決めることになります。
この症状固定は、以下に述べるように非常に重要な区切りになります。
2 症状固定と損害項目
典型的な損害項目を参考に見て行くと、症状固定の前後で、以下の損害が区切られます。
(症状固定前)
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・入通院慰謝料
(症状固定後 ※後遺障害が残存することが前提です)
・逸失利益
・後遺障害慰謝料
すなわち、症状固定後は、治療費、それに伴う交通費、休業損害、入通院慰謝料が請求できなくなります。
後遺障害が残存しないケースの場合には、逸失利益や後遺障害慰謝料が請求できないことから、症状固定によって損害が区切られることになります。
3 症状固定後の治療費
症状固定のタイミングをどうするのかについては、以前、このコラムに記載したことがありますが、症状固定後の治療費は、原則として加害者側には請求できません。
症状固定とは、「怪我の治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない」という状態のことを言いますので、治療費を負担して治療を継続する必要性が失われていると判断されるためです。
そのため、もし、治療を継続したい場合には、健康保険に切り替えて自費負担で行っていただく必要があります。
実際には、保険会社の打ち切り後に、健康保険に切り替えて自費で通院し、痛みは残存するものの、例えば、むちうちであれば、半年が経過したために症状固定にして後遺障害申請を行うといったことがあります。
この場合、実際には、交通事故の被害者の方には、まだ痛みは残存しており、治療を継続したいという意向をお持ちの方がいます。しかし、後遺障害診断書を作成し、そこに症状固定日と記載された日以降は、保険会社は基本的には治療費を負担することはありません。
したがって、症状固定日については、このことをよく考えて、医師と相談する必要があります。
交通事故の被害に遭われ、通院を継続している中で、このようなことまで考えて生活するのは非常にストレスが多いと思います。
保険会社から打ち切られた後に、治療を継続するか悩んでいるという方もいると思います。
交通事故の被害に遭われ、お困りの方は、上山法律事務所にご相談ください。
病院との付き合い方
交通事故の被害に遭われ、お怪我を負った場合、病院に入通院される方がほとんどと思います。
整骨院に通院する際の注意点については、当コラムで既に掲載している通りですが、本日は、病院に通院する際に、弁護士として交通事故の被害者の方に接していてよく思うところを書いていきたいと思います。
交通事故の被害者がお怪我を負った場合、一番多い部位は、整形外科領域になると思います。その中でも、追突等によって、むちうちに悩まれる方に多くお会いします。
むちうちの場合、画像上明確に骨折や神経の損傷が見られるケースは多くなく、被害者の方の訴える痛みを前提に、医師も様々な角度から診察していると思います。
しかし、中には、「それほど大した症状ではない」という前提で診察に当たっているお医者さんもおり、交通事故の被害者の方から「主治医に痛みを訴えても取り合ってくれない」等と言われ、病院や主治医の先生と上手く関係を築くことができないケースもあります。
特に、むちうちの場合、交通事故から3カ月程度が経過すると、保険会社から主治医に医療照会がなされるケースがあります。主治医が「軽快」とか「休業の指示はしていない」といった回答をすることで、保険会社は、それを治療費打ち切りの根拠とされてしまうこともあります。
最終的に後遺障害の認定まで見据えた場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があるため、うまくコミュニケーションが取れない場合には、私どもとしては転院を勧めることもあります。
しかし、交通事故からあまり間が無い状況であればともかく、相当程度通院実績が経ってからの転院は、その理由を勘繰りたくなるところもあろうかと思われますし、そもそも、仕事やご自宅からの距離等の都合で転院の選択自体が持てないという方もいると思います。
対策の難しい問題ではありますが、自分の感じている痛みについては、医師に一貫して伝えるようにして、カルテに残してもらうことを心掛けることが必要です。
後遺障害診断書の作成の段階では、医師によっては、「自覚症状」の欄を空欄やそれに近い内容で作成していたり、必要な検査がなされていないこともあります。
そのため、私ども上山法律事務所では、後遺障害診断書の作成をお願いする際には、病院に同行させていただいたり、主治医の先生にお手紙をお送りしたりしています。
このように、交通事故の被害者の方は、通院しておけばよいというわけではないことを頭に入れておく必要があります。
事故に遭われて、痛みと闘いながら、色々なことを考えなければならない状況の中で、病院についてまで気を回さなければならないのは相当に大変ですが、示談交渉に向けて、症状固定前の通院中であってもアドバイスを得られる弁護士の存在は重要です。
そのため、事故直後から依頼されることをお勧め致します。
通院中にお悩みを抱えている交通事故被害者の方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
整骨院治療について
交通事故の被害に遭われた方で、整骨院に通院される方も多いと思います。
整形外科に比べて遅い時間帯にも対応してくれる傾向もあることから、お仕事をされている方は、整形外科より整骨院の方が頻回に通院しているという案件もよく見受けられます。
しかし、注意が必要です。
整骨院への通院については、保険会社は抵抗を持っています。治療費の打ち切りが整形外科に比べて早まったりすることがあります。また、示談交渉の段階になって、保険会社の方が整骨院への通院の必要性を否定するケースもあります(訴訟の段階に至ると、この傾向は顕著です)。
一般に、整骨院治療は、以下の要件を満たす必要があるとされています。
1 医師の指示がある場合
医師の指示がある場合には、医師による治療の一環といえるからです。
2 医師の指示がない場合
医師の指示がない場合は、医師の指示があったと認められるのと同等の、以下の諸条件を満たす必 要があります。
➀ 施術を受ける必要性があること(整形外科での治療のほかに施術を受ける必要があったか)
② 施術の合理性があること(必要な部位に関して施術が行われたか)
③ 施術の相当性があること(怪我の程度に比して施術内容・期間・費用などが相当だったか)
④ 施術の有効性(施術によって具体的な効果が認められたか)
もっとも、上記1~4の条件が満たされた場合でも、全額の支払いを受けることができるのは稀で割合的な減額がされることもあります。
保険会社の方で、整骨院に費用を支払っていたら、それを容認していたのではないかと思われるかもしれません。しかし、裁判所はそのように認定はしてくれません。
整骨院での通院を継続する場合には、上記の要件を満たすかの確認が必要です。
また、整骨院の通院だけに偏るだけでなく、定期的な整形外科への通院と併用することをお勧め致します。整形外科への定期的な通院があれば、治療継続の必要性は認められやすくなりますし、後遺障害の申請を行う際にも、整形外科への定期的な通院が無いと、後遺障害診断書の作成をお願いする際に支障が出る可能性があります。
治療中の対応方法を間違えないことも重要です。事故に遭われて不安がありましたら、いつでも上山法律事務所にご相談ください。