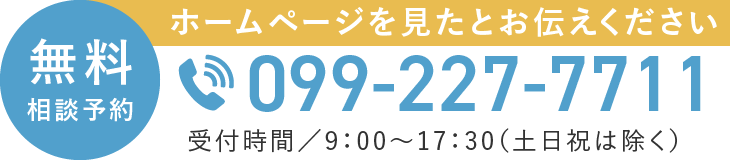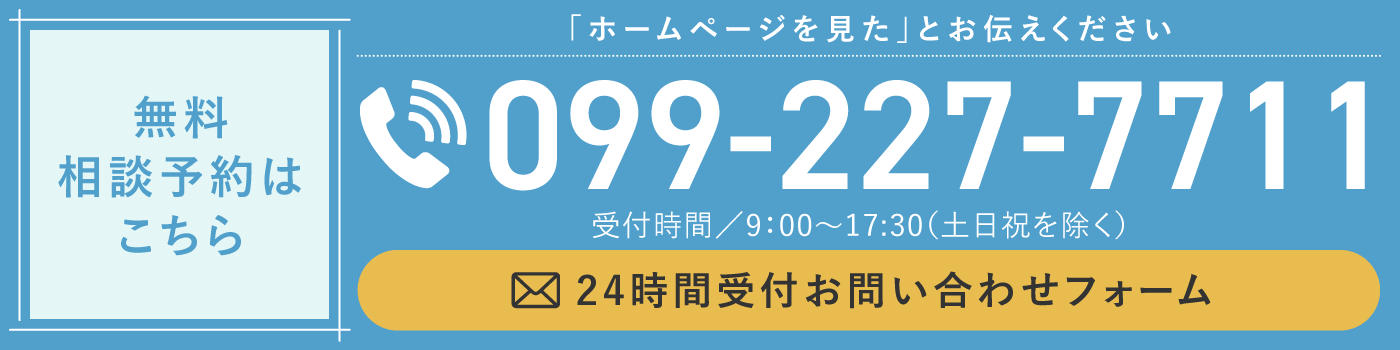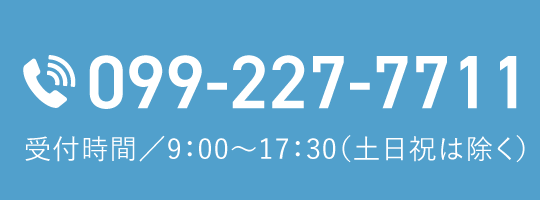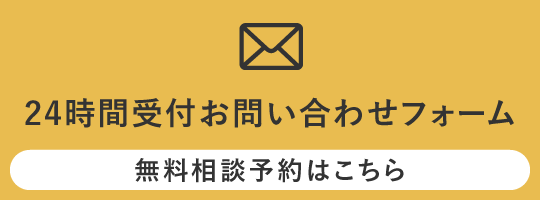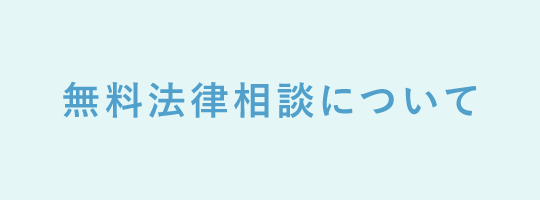Author Archive
経済的全損について
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
物損事故に遭い、相手方に、車両の修理費を請求する際に、経済的全損が問題になることがあります。
2 経済的全損とは
経済的全損とは、修理費用が車の時価額を上回った場合をいいます。
経済的全損と評価されるときの、物損の損害額の計算方法は次のとおりです。
(計算式)
損害額=車両の時価相当額①+買い替え諸費用②
①車両の時価相当額
裁判例では、「自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によって定めるべき」と示されています。
時価相当額の算定当たって参照される資料として、いわゆる「レッドブック」(有限会社オートガイド「オートガイド自動車価格月報」)が広く用いられています。その他、インターネットの中古車販売サイトの取引事例、オークションの販売情報、中古車専門誌上の取引情報などを参考にして算出することもあります。
これらの資料をもとに、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離といった情報をもとに検索し、その平均値などを参考にして評価します。
感覚的なお話になりますが、保険会社は、レッドブックを参考にしていることが多く、中古車販売サイト等の方が高額で算出されているという事案も多く見受けられます。
保険会社が経済的全損と主張して、車両時価額の資料を送付してきても、よく確認することが重要です。
②買い替え諸費用
経済的全損のときには、同種・同等の車両を再取得するためのすべての費用が損害となるため、買い替えにかかる諸費用もまた加害者に請求できます。
買い替え諸費用には、次のものが含まれます。
・登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当額
・登録、車庫証明、廃車等の代行手数料相当額
・自動車取得税
・車両本体価格に対する消費税相当額(買い替え費用ではなく、自動車本体の「時価額」に含まれると整理する考えもあります。)
・事故車両の自動車重量税未経過分(使用済自動車の再資源化等に関する法律)により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)
※ 事故車両にかかる自動車税、自賠責保険料については、いずれも未経過分について還付制度がありますので、損害として認められません。ただし、軽自動車の自動車税は還付されません。
買い替え諸費用の賠償が認められるのは、時価相当額だけ賠償されても車両を再取得できるわけではなく、これらの諸費用の賠償なくしては十分な被害回復ができないからです。
買い替え諸費用はディーラーから見積もりを取得することで算出できます。
ただ、保険会社によっては、買い替え諸費用は、保険会社同士のやりとりではお互い請求しないものである等という趣旨不明な主張を行ってきたこともあり、負担を避けようとするのも事実です。
裁判例で認められている類のものは、そのように強く主張して交渉することが必要です。
3 まとめ
以前から投稿していますが、物損事故は、人損に比べると必ずしも金額が大きく無いケースが多いですが、かといって、簡単に示談できるわけではありません。
経済的全損は、過失割合と並んで問題になることが多い争点です。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
弁護士業務と交通事故案件②
1 はじめに
交通事故の被害に遭った方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償額を獲得することに努めるのが一般的です。
前回、どんな弁護士が交通事故事件を扱っているのかについて、説明させていただきました。
本日は、他の事件と比較したときの交通事故事件の特徴をお伝えします。
2 交通事故案件の特徴
いわゆるマチ弁と言われる弁護士は、交通事故のみを集中的に扱うごく少数の弁護士以外には、離婚・相続といった家事事件、債務整理案件、不動産関係その他の事件も取り扱っています。
マチ弁が扱う事件の中では、建築紛争案件や医療過誤案件が、専門性が高いと言われています。これらの案件は、弁護士だけの力ではおよそ手続きを進めることができず、建築士や医師にも関与してもらう必要があるからです。
もちろん、不動産事件や不動産の絡む家事事件でも、弁護士だけではなく、不動産業者、不動産鑑定士、司法書士といった隣接他業種が絡むこともあります。しかし、上記建築紛争と医療過誤は、弁護士からすると畑違いといいますか、かなり異なる性質のものを扱うことになりますので、そこに難しさがあります。
では、交通事故案件はどうでしょうか。
後遺障害が問題になる事案であれば、医療過誤と同様に医師の協力が必要になることもあります。医学的な知識が必要ということで、他の一般民事事件と比べてもハードルが上がります。
また、受傷機転(打撲や骨折等の外傷を負うに至った原因や経緯のこと)や過失割合の関係で、事故態様が問題となることがあります。この場合には、交通事故工学の観点での知識が必要になることもあります。科捜研OB等が、交通事故解析のための鑑定業務を行っていたりします。
また、刑事事件が絡む場合には、刑事手続の知識や、免許の停止や取消処分が絡む場合には行政手続の知識も必要になります(これはマチ弁でも皆が扱うわけではありません。特に行政手続はほとんど扱わないと思います)。
3 保険の知識が重要
以上、色々な知識が必要なことをお伝えしましたが、交通事故案件に特徴的なものとして一番大きいのは、保険(主として自動車保険)と社会保障の知識だと思います。
このコラムでも、労災の要件を満たす事案であれば、労災を使った方がいいのか、保険会社から打ち切りにあった場合に、健康保険に切り替えて治療を継続するのかといった問題や、自分の加入する人身傷害補償保険の利用をどうするかといったことを記載してきました。
そもそも、事故に遭うと、通常は相手方の保険会社(任意保険)と交渉するわけですが、任意保険とは別に、自賠責保険があり、また、自分の加入する保険がありと、複雑すぎて混乱してしまいそうです。
また、これらの制度や商品の知識とは別に、損益相殺のことも考えておかないといけません。
たとえば、労災給付は、慰謝料はカバーせずに、主として休業損害や逸失利益に費目拘束があり、遅延損害金は発生しないといった判例の知識や、自賠責保険は費目拘束はなく遅延損害金にまずは充当されるといったことです。
4 まとめ
以上見たように、かなり色々な分野が複合的に絡んでいるのが交通事故案件の特徴です。
弁護士はみんな、司法試験に合格しており、民法の知識は一定水準で保証されています。
しかし、交通事故案件を扱うために必要な上記知識は、試験では問われないもので、弁護士になってからの研鑽がものを言います。
当事務所では、複数の弁護士が研鑽しながら、様々な交通事故案件を扱ってきておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
弁護士業務と交通事故案件
1 はじめに
交通事故の被害に遭った方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償額を獲得することに努めるのが一般的です。
これまで、その方法について、このサイトの投稿記事でも様々な情報を掲載してきました。
もちろん、ご本人での対応が難しい場合には、弁護士に依頼をして進めることになると思います。
本日は、交通事故事件を扱う弁護士について、お伝えします。
2 弁護士の仕事
弁護士業務といっても、取り扱う業務内容はまちまちです。
企業法務と言われる会社の案件を中心に扱う弁護士もいれば、いわゆるマチ弁と言われる個人の依頼者からの依頼を中心的に扱う弁護士もいます。
交通事故は主に後者の弁護士が取り扱うことが多いですが、この中でも、離婚・相続といった家事事件や、債務整理等の案件も扱いながら交通事故を扱う弁護士もいれば、交通事故案件そのものを集中的に扱う弁護士もいます。
当事務所は鹿児島県弁護士会に所属する弁護士ですが、私どもの知る範囲では、鹿児島の弁護士の中で、交通事故だけを扱っている弁護士はいないのではないかと思います。様々な案件に対応しながら、その中で交通事故事件の占めるウエイトが多いか少ないかという違いになると思います。
近年、交通事故案件は、リスティング広告が高額になっていたり、弁護士の中でも力を入れている方とそうでない方がおり、相対的に事件が回らず、ほとんど扱わないか、年に数件しか扱わないという弁護士もいると思います。
一方、保険会社の顧問弁護士という形で、主として加害者の側で活動する弁護士は一定数います。このような形で関与している弁護士は、相対的に見て、交通事故の取扱件数は多いと思います。ただ、特定の保険会社とは利害関係があるために、被害者側の代理人として活動ができないという制約があったりします。
当事務所は、保険会社の顧問弁護士はしておりませんので、このような制約はありません。
3 まとめ
交通事故の被害に遭われた方で、対応にお困りの方は、弁護士に相談・依頼をされることをお薦めいたします。
上記の通り、弁護士交通事故を取り扱う弁護士にどのような種類があり、どのような仕事をしているかといったことを記載しましたので、参考にしていただければ幸いです。
当事務所では、コンスタントに交通事故案件に携わっておりますので、お困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
物損事故に関する評価損について
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた場合、相手方の保険会社と示談交渉することになると思います。
本日は、物損についてお話をします。
物損では、修理費用の請求するのが典型的ですが、これは、相手方の保険会社と修理工場が協定を結んで修理費用について争いの無いように進めることが多く、この場合には、修理費用の額そのものが争いになることは少ないと思います。
では、自身の車両が新車であり、修理をしたとしても車の価値が下がってしまうといった事情はどう評価されるのでしょうか。
2 評価損とは
交通事故を原因として車が事故車となってしまったことにより、その車の価値が下がってしまうことを「評価損」といいます(「格落ち損」ということもあります)。
車の評価損には、大きく分けて以下の2種類があります。
①技術上の評価損
②取引上の評価損
①技術上の評価損とは、交通事故によって車の性能・機能に修理不可能な損傷が生じることによって価値が下落することをいいます。
②一方、取引上の評価損とは、車の性能や機能が損なわれたかどうかとは関係なく、(仮に完璧に修理されていたとしても)車の買い手は事故車を欲しがらないという中古車市場の傾向のために、事故車の価値が下がってしまうことをいいます。
3 認められるか
評価損は、そもそも評価損を認めるかどうか、認めるとしていくらか、などを算定することが難しく、簡単には行きません。
車の査定を行う第三者機関としては、「一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)」がよく知られています。
交通事故により車の価値が下がってしまった場合には、日本自動車査定協会に申請を行うことにより、査定の上で「事故減価額証明書」を発行してもらうことができます。
事故減価額証明書は、保険会社との交渉や損害賠償請求訴訟などの際に証拠として利用することが可能です。
ただ、これが裁判所を拘束するかというと、そうではなく、裁判所は、その他の証拠等を踏まえて判断を下すことができます。
ただ、実務的には、まず、事故減価額証明書を取り付けてもらい、保険会社と交渉で解決ということが多いと思います。
当事務所でも、最近、ご依頼をいただいた案件で、事故減価額証明書の全額では無かったですが、修理費の10%を評価損として認めるということで、訴訟外で示談したケースもあります。
4 まとめ
物損事故は、人損に比べると必ずしも金額が大きく無いケースが多いですが、かといって、簡単に示談できるわけではありません。
今回の記事で問題になっている評価損や、経済的全損の場合、レンタカー代等は損害がどの程度認められるかが問題となることが多く、過失相殺も互いに一歩も譲らず裁判になるということも多いです。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
こちらの過失が大きい事故の場合
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方で、自身にも過失が問われて過失相殺が問題となることはよくあると思います。
こちらの過失が大きいと評価されるケースの場合、どのように処理すべきでしょうか。
(こちらの過失が大きいわけですので、こちらを被害者、相手方を加害者と呼んでいいのかという問題もありますが、ひとまず、この点は措いておきます)
2 物損について
交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っている場合には、弁護士の立場からすれば、受任すること自体に躊躇はありません。
その上で、できうる主張をして少しでも相手方と過失割合について調整を図るということになるだろうと思います。
しかし、弁護士特約に入っていないとなると、悩ましいです。
修理費用にもよると思いますが、過失割合で何とか上手い解決に結びつけられたとしても、そこで獲得できる差額よりも、弁護士の着手金の方が高額になってしまうケースもあるからです。
このようなケースの場合には、人損も生じていて、そこから一定程度の損害賠償金を獲得できる見通しでなければ、交通事故の被害者の方にとって、弁護士に依頼することによる経済的メリットが無いということになってしまいます。
3 人損について
物損と同様、交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っていれば、弁護士の立場からすれば、受任することに躊躇はありません。
しかし、交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っていない場合で、被害者の過失が大きいときには、受任すべきかどうか悩みます。
まず、相手方の主張内容が正しいのか、事故状況や事故現場を調査します。
その上で、症状等から予想される総損害額を見通して、先方の主張と当方の主張する過失割合を比較して、弁護士に依頼する経済的メリットがあるかどうかを検討することになります。
過失割合を争うのが難しそうな場合、あるいは、争ったとしても、経済的メリットのなさそうなケースの場合には、ご自身で被害者請求をすることをお勧めしています。自賠責は7割以上の過失の場合しか減額されないため、交通事故の被害者の方に過失が大きい場合には、自賠責に請求するのが一番回収額が大きくなる可能性もあるためです。
4 まとめ
以上のとおり、弁護士に依頼すると、経済的には赤字になってメリットが無いというケースも世の中にはそれなりに存在します。
しかし、交通事故に遭い、どのように対処したらいいのかお困りなのは、どちらでも変わらないと思います。
そのようなときには、相談だけでも弁護士にしてみることをお勧めします。
交通事故の被害に遭われて、お困りの方は、上山法律事務所にご連絡ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
交通事故訴訟の進み方
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、通常、相手方の保険会社と示談交渉を行います。しかし、相手方の保険会社の提示する金額に納得ができない場合には、訴訟によって解決を図ることになります。
どこの裁判所で行うことになるのかという問題については、前回のコラムで記載しましたので、
今回は、裁判が実際にどのように進んでいくのかということをお伝え致します。
地方裁判所と簡易裁判所で大きく違いはありませんが、主として地方裁判所の進め方を前提にしています。
2 流れ
(1)訴状
まず最初に、裁判所に訴状を提出します。
訴状には、事故の状況、入通院経過、症状、損害等をまとめて整理したものを記載します。
その際に、特に事故態様については、
・車両の損傷状況の写真
・事故現場の写真や動画
・これらを図面にしたもの
を提出するのが、裁判を早く進めるために望ましいです。
刑事事件になっていれば、警察の作成した実況見分調書を取り付けて提出するという方法をとるのが一般的です。
そうでない場合には、原告側で現場に行って撮影したりして、図面に起こします。
後遺障害について争いがある場合(原告になる交通事故の被害者方の方で、自賠責等が認定した後遺障害結果に不服がある場合)には、その根拠となる資料を早めに準備し、訴状に盛り込めると審理の早期化に資すると言えます。
裁判所に訴状を提出すると、概ね1か月から1か月半後に、第1回口頭弁論期日が指定されます。
(2)答弁書
第1回口頭弁論期日までに、被告側が答弁書を提出します。だた、被告側は一方的に訴えられる関係にありますので、第1回口頭弁論期日は出席せずに、第2回期日までに反論するという形で、簡単な答弁書を提出することも認められています。
第2回期日以降も、概ね1か月から1か月半に1回くらいのペースで裁判は進んで行きます。
(3)準備書面での整理
その後は、準備書面の提出という形で、争点についてお互いの主張立証を尽くしていきます。
訴訟に発展する交通事故事案の争点としては、
・事故態様と過失割合
・後遺障害の程度
・損害
について、争点になることが多いです。
訴訟の開始から半年から1年くらいで、争点整理が終わります。
(事案によっては、もっと早く整理ができる事案もありますし、2年以上争点整理に時間を要する事案もあります)
(4)和解勧試
争点整理が終わると、裁判所から暫定的な心証に基づいて和解案が示されることが多いです。
この段階で、お互いが納得すれば、和解によって裁判は終了します。
和解の席には、当事者ご本人の方が出席する義務はありませんが、事案によっては、裁判所から出廷を求められることもあります。
往々にして、原告の主張の全てが裁判所の心証によれば認められない事案で、求められることが多い印象です。
(5)本人尋問・証人尋問
前述の和解ができないと、本人尋問・証人尋問の手続きになり、裁判所に出廷して直接お話を伺うことになります。
これには、事前の準備等もあり、交通事故の被害に遭われた方が当事者として手続きに関与する中では、一番濃い関与の仕方になると思います。
(6)判決
以上の尋問手続が終了すると、裁判所から改めて和解勧試がある場合もあり、それで話し合いがつけば裁判は終了となります。
しかし、話し合いが付かないと、判決言い渡しになります。
(7)控訴・上告
1審の判決に不服があれば控訴、高等裁判所の判断に不服があれば上告ができます。
3 まとめ
以上のように、裁判の流れをお伝え致しました。
以下は、あくまで当事務所の感覚です。
事件の終わり方としては、和解による終了がほとんどで、判決に至るケースは、全体から見ると稀です。
ただ、判決に進んだケースのほとんどは、和解で解決ができなかった事案になりますので、控訴に至っている印象です。
時間的には、和解できる事案については、訴訟提起から6~12カ月以内(10カ月くらいが一番多い?)での解決が多いのではないでしょうか。その場合には、交通事故の被害者の方ご本人は、1度も裁判所に出向かなくて済んだというケースが多いと思います。
あくまで当事務所の感覚になりますが、参考にされてください。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
どこの裁判所で裁判するのか
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、通常、相手方の保険会社と示談交渉の話し合いをすることになると思います。
これは、物損事故も人身事故でも変わりありません。
話し合いで解決ができない場合には、訴訟=裁判で解決を図ることになると思います。
訴訟提起するのは、通常は、もっと賠償額は高額なはずだということで、交通事故の被害者の側から行うのが通常です。
この場合、どこの裁判所で裁判をすることになるのでしょうか。
2 場所は?
原則としては、被告の住所地を管轄する裁判所になります。これは、一方的に訴えられる被告側に準備の機会を与えるためだと言われています。
ただ、交通事故の損害賠償請求のような金銭請求の事案について、義務履行地に訴訟提起することもできます。本来、債務者=加害者から債権者=被害者にお金を持参して支払うという原則があるため、支払義務は被害者の住所地になることから、被害者の住所地を管轄する裁判所でも訴訟提起できます。
また、事故発生地を管轄する裁判所でも訴訟提起できます。
このように複数の裁判所が管轄を持つこともあります。
3 地方裁判所と簡易裁判所
裁判制度は三審制ですが、民事訴訟の場合、1審の裁判所は、簡易裁判所と地方裁判所があり得ます。
これは、請求額が140万円以下かどうかで区別されます。
ただ、140万円以下の場合(物損はほとんど該当すると思います)で、簡易裁判所に訴訟提起をしたとしても、事案が複雑なときには、簡易裁判所の方から、地方裁判所に職権で移送することもあります(裁量移送といいます)。
地方裁判所と簡易裁判所の違いですが、これから先は、法律的な根拠に基づくものではなく、私どもの私見です。
一般論としては、地方裁判所の方が、当事者の主張や証拠を精密に検討しています。最終的には、どちらの裁判所であっても、和解によって終了することがほとんどですが、審理については、地裁の方が緻密で長くかかる印象です。
簡易裁判所は、言い方は悪いですが、ある程度ざっくりと、早期解決を目指すという印象を受けます。簡易裁判所に特徴的なものとして、司法委員という裁判官以外の有識者(交通事故案件であれば、かつて、保険会社に長く勤務していた方等)に裁判に立ち会わせて、和解協議をさせることもあります。地裁よりも1回の裁判期日に長く時間をとって、ざっくばらんに話を聞いて早期解決を目指すという形を目指しているのかもしれません。
4 まとめ
以上のように、交通事故の被害者の方が裁判を選択した場合に少しでもイメージができるように記載してみました。
当事務所では、交通事故の被害者の方が、保険会社の提示額に納得されない場合には、訴訟による解決を進めており、豊富な実績があります。
交通事故の被害に遭われた方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
交通事故と破産事件②
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、正当な損害賠償金を獲得するために、相手方の保険会社と示談交渉するのが通例です。
しかし、これはあくまで一般的なケースを想定したものです。
相手方が、任意保険に加入していない場合、この前提が崩れます。
無保険の場合については、当ホームページで簡単に概要をご説明しています。
強制保険と言われる自賠責や、政府保証事業については、いわば1階部分となります。
そのため、ご自身が人身傷害保険に加入していなかったり、適用対象外の事故の場合、相手方から直接、2階部分(本来は任意保険会社から支払ってもらう部分)について回収しなければなりません。
2 加害者に支払能力がない場合
事故がさほど大きいものではなく、2階部分が多額にならなければ、加害者が手出しをして支払うことができるかもしれません。
しかし、重度の後遺障害が残存したり、死亡事故の場合はどうなるでしょうか。
賠償額も高額になるため、加害者が支払うことができないという状況もありえます。
その場合、長期の分割払いの提案があったり、破産申し立てをされてしまう可能性があります。
3 加害者が破産するとどうなるか
加害者が破産の申し立てを行った場合、破産手続の中では、交通事故の被害者の損害賠償請求権は、破産債権という扱いになります。
破産した加害者に、債権者に配当できるような資産があれば、それをお金に換えた後に金銭の形で配当されます。しかし、配当率は低く、少額になるのがほとんどです。そもそも、配当できるような資産が無ければ、それも見込めません。
その後、加害者が、免責決定を受けると、原則として債務はチャラになってしまいます。
交通事故の被害者の方から見れば、まさに泣き寝入りです。
しかし、破産法では、以下の場合には非免責債権として扱われています。
① 悪意で加えた不法行為
② 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
①についてですが、「悪意」とは、単なる故意ではなく、「不正に他人を害する意思ないし積極的な害意」を意味するとされています。
交通事故の場合でいえば、被害者に保険金をかけて、あえてひき殺すような、著しく悪質なケースが想定されます。
②についてですが、まず「生命身体に対する」とされているため、物損は対象外です。物損は、悪意がない限りは全て免責されます。
また、「重大な過失」とは、「故意に匹敵するほどの著しい注意義務違反」を指します。
具体的には酒酔い、無免許、危険運転致死傷罪に該当する危険運転などの場合が想定されます。また、他にも、事故の具体的な態様によっては、重大な過失と認定される可能性があります。
一方、重過失とまではいえない通常の過失、不注意により生じた生命または身体を害した場合の損害賠償請求権は含まれませんので、自己破産により免責されます。
以上については、明確な基準があるわけではありませんので、最終的には、当該事故の態様から、ケースバイケースの判断となると思います。
4 まとめ
相手方が任意保険に加入しておらず、相手方から直接、賠償金を回収しなければならない場合には、以上の点にも注意して対応しなければなりません。
お困りの場合には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
なお、任意保険に加入している交通事故の加害者が破産した場合には、任意保険は、直接、被害者に支払いを行うことになっているようです。先日、当事務所で破産管財人として対応したケースでも、任意保険会社はそのように対応していました。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
交通事故と破産事件
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方の中には、事故前から生活に苦しんでいる方も多いと思います。
交通事故の示談交渉で高額の賠償金を獲得できれば、それを債務への返済に充てるということもあり得ると思いますが、賠償金では完済ができずに多額の債務が残ってしまう…こういった事例も、実は世の中では多く見受けられます。
このように、交通事故の被害に遭われた方が多重債務者である場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
2 破産するまでの必要が無いケース
まず、破産するまでの必要が無いケースの場合には、通常通り、交通事故の被害者として示談交渉を行い、できうる限り最大限の賠償金を獲得するよう努力することになります。
その賠償金を、どのように使うかは原則は自由です。
破産しないということであれば、否認(特定の債権者にだけ有利な弁済をした場合等に、それを破産手続の中で破産管財人が否定する制度です)のリスクもありません。
3 破産を検討するケース
(1)破産手続開始前に示談してい場合
前述の通り、獲得できそうな賠償金では債務の返済について目途が立たない場合には、注意を要します。
まず、破産手続に入る前に示談して賠償金を回収した場合には、それまでの預貯金等を含めた他の資産と合わせて99万円の範囲までは、自由財産ということで手元に残すことができると思いますが、それ以上の金額については、原則としては、破産財団(破産管財人が債権者に配当するための原資となるものです)に組み入れる必要があります。
破産の準備等に入りそうな時期に、破産財団にそのお金を引き継ぐことなく浪費した場合には、免責不許可事由(チャラにしてもらえない事情)になる可能性があります。
(2)破産手続に入る前に示談していない場合
次に、破産手続に入る前に示談していない場合です。
この場合は、損害項目によって、破産財団に組み入れるかどうかが変わってきます。
治療費については、保険会社が医療機関に直接支払っているものと思われますし、そのような処理に問題はないと思います。
休業損害や、後遺障害が残存した場合の逸失利益については、原則として破産財団に帰属します。しかし、これらは、破産者の将来の自由財産の減少分を補填するという意味があり、個別事件ごとに自由財産の拡張が認められるべきであると考えられています。
慰謝料については、金額が定まっていない時点では、自由財産になり、裁判や合意により金額が確定した段階では、破産財団に帰属することになります。ただし、慰謝料は、被害者の人格的価値の毀損に対する損害の填補であるので、その全てを破産財団に帰属させるのは妥当ではなく、かなりの割合で自由財産の拡張が認められるべきではないかと考えられています。
このように、破産手続に入ってからは、明確な指標はありませんが、破産手続前に比べると、交通事故の被害に遭った方の手元に残せるものが多そうな感じです。
3 まとめ
以上のように、多重債務者の方が交通事故の被害に遭われた場合、いつのタイミングで示談をするかも重要な問題になります。
ただでさえ苦しい中、事故にも遭われてより苦しいという状況かと思います。
お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
交通事故と行政事件
1 はじめに
交通事故が発生し、事故を起こしてしまった場合、民事的には損害賠償請求、刑事的には過失運転致死傷罪等で捜査がなされる可能性があります。
では、行政処分についてはどうでしょうか。
交通事故で問題となる行政処分は、主に違反点数と、それを基にした免許停止あるいは免許取消処分のことです。
2 違反点数制度と処分
警視庁のホームページに、違反点数一覧表があります。
当ホームページでも飲酒運転についてまとめています。
飲酒運転について | 鹿児島で交通事故・後遺症でお困りなら無料法律相談対応の弁護士法人かごしま上山法律事務所にお任せください (kagoshima-koutsujiko.com)
例えば、呼気中アルコール濃度0.15mg以上~0.25mg未満の酒気帯び運転の違反点数は原則として13点です。13点は前歴がない方にとっては免許の停止90日となります。
0.25mg以上の酒気帯び運転は違反点数25点となり、免許の取消(欠格期間2年)となります。
一方、正常な運転ができないほど酔っていたと判断され、酒酔い運転となった場合、違反点数は35点となり、免許の取消(欠格期間3年)となります。
3 実際の手続き
免許停止、取り消しに至らない違反点数の場合には、反則金を納付して終了ということにな
ると思います。
警視庁のホームページに、反則行為の種別及び反則金一覧表があります。
免許停止あるいは免許取消の処分が予定されている場合には、意見の聴取が行われます。
意見の聴取とは、処分が公正に行われるよう、運転者が意見を述べ、自己に有利な証拠を提出する機会を与えるための手続きです。
出頭通知書に指定された日時・場所(警察署や運転免許センターなど)で違反についての具体的な事実確認が行われます。
違反者の主張が正当と認められた場合は、処分が軽減されることも予定されている制度で
はあります。
代理人を出席させたり、弁護士と一緒に出席することもできるようになっています。
4 最後に
最近、飲酒運転絡みでこの種の問い合わせが増えています。例えば、お酒を飲んだまま駐車場で寝ていて、起きて運転したら…といったものもありました。
率直なところ、この種の行政手続に弁護士が関与することは極めて稀だと思います。
ただ、交通事故によって、上記違反点数の問題だけでなく、物損や人損の民事事件や刑事事件が絡むケースもあると思います。
ご家族がこのような問題に遭遇する可能性もあると思います。
交通事故が発生し、初動からどのように対応したらいいか分からないという方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。