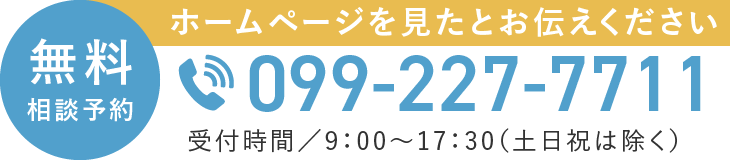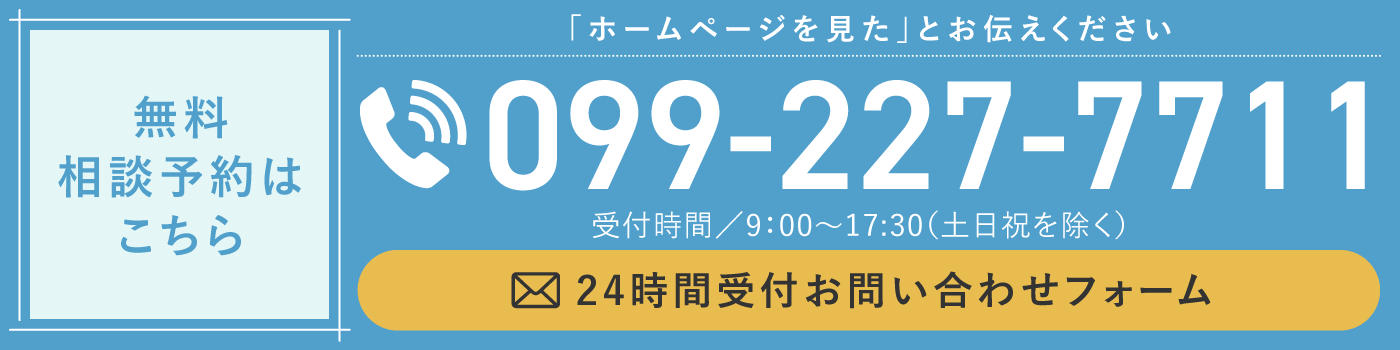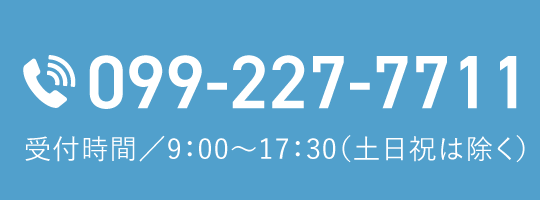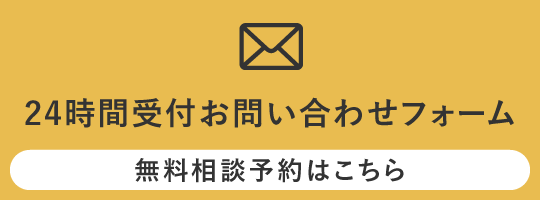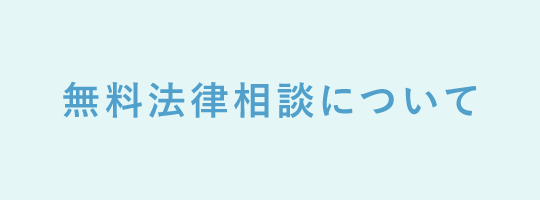Author Archive
入院雑費
1 はじめに
交通事故の被害に遭われて、お怪我の程度が大きく、入院を要する方もいらっしゃると思います。
入院中に必要な入院費、治療費については、原則として、加害者の加入する保険会社に負担してもらうことになります。
では、入院中に掛かった諸経費についてはどうでしょうか。
法律的には、これを入院雑費といいます。
2 入院雑費とは
日常雑貨品(衣類等)、栄養補給品、通信費(電話、郵便等)、文化費(新聞、雑誌、テレビ利用券代等)等、かなり広範囲の雑費を含んでいます。
この入院雑費ですが、基準となる金額が低額化されています。
例えば、自賠責保険の基準では、1日当たり1100円とされています。
裁判基準では、1日当たり1500円とされています。
このように定額化された金額を請求する場合には、領収書は必要ありません。
実際の示談交渉の場面では、保険会社側は、裁判基準の1500円ではなく、1100円で提示してくることが多い印象です。
入院期間が少なければ、結論に大きな影響はないかもしれません(それよりも、慰謝料の方が裁判基準と保険会社の提案額に大きな差があることがほとんとで、主戦場はそちらになっている事案が多いのではないでしょうか)。
ただ、重症で入院期間が長かったり、骨折後にボルトを入れており、除去のために複数回入院し、結果として入院期間が累積的に長い日数になった場合等は、見過ごせない差になることもありますので、注意が必要です。
3 基準を超える場合
明らかに上記の日額の基準では足らず、定額化された金額を超えるというケースもあると思います。
入院雑費は、入院によって通常必要であると考えられるものを念頭に置いています。場合によっては、通常の範囲を超えて入院雑費を支払わなければならないことも考えられます。
このような定額の入院雑費以外にも、必要かつ妥当な実費が、個別に損害として認定される余地があります。そのため、領収書等を保管しておく必要があります。
重度後遺障害が残存した場合のおむつ代等、裁判例で認められているケースもあります。
4 まとめ
以上の通り、交通事故の被害に遭われた方に、保険会社から損害の提示があった際、特に疑問を抱くことなく、入院雑費を眺めていらっしゃるかもしれません。
本当はもっと支出していたはずだと疑問に思われたりした場合には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
通院交通費について
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方で、お怪我を負った場合、事故直後から整形外科等の病院に通院されると思います。
その場合、交通費の請求が問題となります。
徒歩圏内で、かつ徒歩での通院が可能であれば、原則として交通費の負担も問題にならないと思います。
ただ、一般的にはそのようなことはなく、何らかの形で通院に時間や費用をかけていると思います。
交通費は、必要性、相当性が認められれば相手方に請求できます。
治療の必要性が認められ、かつ、距離的にも自力での通院が困難であれば、交通費支出の必要性は認められます。
では、相当性の観点ではどうでしょうか。
2 公共交通機関の場合
バスや電車の場合、基本的には、支出した分を請求できると思います。
新幹線は、それだけの遠距離になってもその医療機関に通院する必要があるか、また、新幹線を利用するだけの事情があるか(移動時間をできるだけ短くする必要があるような症状がある場合)といった観点から、極めて例外的に認められると思います。
3 タクシーの場合
タクシー代に関しては、タクシーの利用が相当とされる場合に限って交通費として支払いが認められます。
よって、タクシー代を通院交通費として請求するためには、タクシー利用の必要性について、一般的・客観的に見て納得のいく理由があることが必要です。
徒歩で公共交通機関まで行くのが非常に困難な場合等が考えられると思います。
ただ、仮にこのような事情があったとしても、症状固定までの全期間が当然に認められるわけではなく、例えば、事故から数カ月経過した後は、公共交通機関に切り替えることが可能だったのではないかという指摘が来ることもあり得ます。
タクシー代は高額になる傾向があるため、相手方の保険会社ともよく話し合っておく必要があると思います。
4 自家用車の場合
鹿児島のような地方の場合、これが一番多い手段だと思います。
この場合、ガソリン代、高速料金代、駐車場代などを通院交通費として請求できます。
自家用車を利用する場合は、タクシーよりも交通費の支出を抑えようとしていると考えられるため、ガソリン代などが損害として認められやすくなっています。
ガソリン代については、自宅から病院までの距離をもとに1kmあたり15円として計算するのが実務で定着しています(現実に出費した金額ではありません)。
例えば、10km離れた病院に20日間通院した場合のガソリン代計算は以下の通りです。
10キロ×2(往復)×20日(通院日数)×15円=6000円
5 まとめ
通院交通費は、休業損害や慰謝料等に比べると、相対的には金額も大きくはありませんが、長期間に亘る通院等の場合には、積算すれば、無視できない金額になることもあります。
特に、公共交通機関やタクシーを利用した場合には、原則として領収書も必要になります。
事故直後の段階から、証拠収集も含めて弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
症状固定後の治療費
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方が保険会社に加入していれば、原則としては、相手方の保険会社が治療費を直接、医療機関に支払うという扱いになることが多いと思います。
一定期間、治療を継続し、症状固定になれば、示談交渉が始まります。
この一定期間については、事故態様や傷害の程度により様々ですが、むちうちの場合は長くて6カ月程度、整形外科領域で骨折があると6か月から1年程度、頭部外傷だと1年から1年半くらいというのが、大まかな整理です(本当に大まかではあります)。
症状固定とは、「怪我の治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない」という状態のことですが、基本的には主治医のアドバイスに従ってタイミング等を決めることになります。
この症状固定は、以下に述べるように非常に重要な区切りになります。
2 症状固定と損害項目
典型的な損害項目を参考に見て行くと、症状固定の前後で、以下の損害が区切られます。
(症状固定前)
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・入通院慰謝料
(症状固定後 ※後遺障害が残存することが前提です)
・逸失利益
・後遺障害慰謝料
すなわち、症状固定後は、治療費、それに伴う交通費、休業損害、入通院慰謝料が請求できなくなります。
後遺障害が残存しないケースの場合には、逸失利益や後遺障害慰謝料が請求できないことから、症状固定によって損害が区切られることになります。
3 症状固定後の治療費
症状固定のタイミングをどうするのかについては、以前、このコラムに記載したことがありますが、症状固定後の治療費は、原則として加害者側には請求できません。
症状固定とは、「怪我の治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない」という状態のことを言いますので、治療費を負担して治療を継続する必要性が失われていると判断されるためです。
そのため、もし、治療を継続したい場合には、健康保険に切り替えて自費負担で行っていただく必要があります。
実際には、保険会社の打ち切り後に、健康保険に切り替えて自費で通院し、痛みは残存するものの、例えば、むちうちであれば、半年が経過したために症状固定にして後遺障害申請を行うといったことがあります。
この場合、実際には、交通事故の被害者の方には、まだ痛みは残存しており、治療を継続したいという意向をお持ちの方がいます。しかし、後遺障害診断書を作成し、そこに症状固定日と記載された日以降は、保険会社は基本的には治療費を負担することはありません。
したがって、症状固定日については、このことをよく考えて、医師と相談する必要があります。
交通事故の被害に遭われ、通院を継続している中で、このようなことまで考えて生活するのは非常にストレスが多いと思います。
保険会社から打ち切られた後に、治療を継続するか悩んでいるという方もいると思います。
交通事故の被害に遭われ、お困りの方は、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
既払金の扱いについて
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方が、交通事故の加害者の方と示談交渉を行う際、既に支払われた金額についての処理が問題になることがあります。
例えば、典型的なのは治療費です。
治療費は、相手方の保険会社と過失割合の認識に大きな開きが無い限りは、保険会社が病院に直接支払いを行っていると思います。
これは、後から既払金として差し引かれます。
その他にも、休業損害が内払いされているようなケースもあります。
では、これら既払金については、そのまま全て差し引きされるべきなのでしょうか。
2 費目拘束
これらの既払金を差し引くかどうかは、法律的には、損益相殺の対象になるかという形で表現されます。
実際には、費目拘束があるかどうかという点が重要になります。
例えば、労災にも該当するような交通事故の場合に、労災から休業補償給付を受給したものについて、慰謝料からも差し引きを認めるかといいった形で問題となります。
特に、過失相殺が問題となる事故の場合には重要です。
単純化すると、事故により以下の損害が発生したとします。
過失割合は3対7で、こちらが3割引かれるとします。
治療費 20万円
休業損害 20万円
慰謝料 60万円
過失割合 30万円▲
損害額 70万円
では、労災から受け取った休業損害が20万円あったとします。
この場合に、損害費目に拘束が無く、損害から全部差し引きができるという処理をした場合、
70万円―20万円=50万円が請求額になります(※ 細かな話をすると、過失相殺の後に労災を差し引くのか、労災を差し引きしてから過失相殺をするのかという問題もあるのですが、判例は前者のため、そのような前提で記載しています)。
では、労災から受け取った休業損害は、20万円からしか差し引きができないとします。
その場合、過失3割が控除されるとすると、
治療費 20万円×0.7=14万円
休業損害 20万円×0.7=14万円
慰謝料 60万円×0.7=42万円
ここから、休業損害に20万円を充てるとすると、―6万円=0円となります。
残りの治療費14万円+慰謝料42万円=56万円が請求額となります。
以上のように、損益相殺の対象となる既払金について、費目拘束があるかどうかは、損害の計算に当たって、非常に重要な意味を持ちます。
3 実際にどうなっているのか
以下、それぞれの種類毎に整理しておきます。
① 加害者の弁済
加害者からの弁済は、弁済の趣旨によりますが、全損害への填補の趣旨の場合は、全損害から控除されます。
② 自賠責保険から支払われた損害賠償額
自賠責保険から支払われた損害賠償額は、人的損害に対するものです。物的損害には填補されないので、物損からは控除されません。人損については、いかなる損害名目で支払われたとしても、人損の全損害から控除されます。
③ 加害者側の任意保険会社からの支払い
任意保険会社からの支払いのうち、対人分は人損全体から、対物分は物損全体から控除されます。
④ 労災保険給付と損害費目との対応関係
保険給付の種類ごとに、控除できる損害費目との対応関係があります。
( )は通勤災害の場合です。
・療養補償給付(療養給付)→治療費
・介護補償給付(介護給付)→将来介護費
・遺族補償給付(遺族給付)→死亡逸失利益
・休業補償給付(休業給付)、傷病補償年金(傷病年金)、障害補償給付(障害給付)→休業損害と後遺障害逸失利益の合計
・葬祭料(葬祭給付)→葬儀費用
・慰謝料→なし
・特別支給金→なし
⑤ 国民年金・厚生年金と損害費目との対応関係
年金の種類ごとに、控除できる損害費目の対応関係があります。
(国民年金)
・障害基礎年金→休業損害、後遺障害逸失利益
・遺族基礎年金→遺族基礎年金
(厚生年金)
・障害厚生年金→休業損害、後遺障害逸失利益
・遺族厚生年金→死亡逸失利益
4 最後に
以上見たように、損害の計算において、既払金がどのように扱われているかは非常に重要です。保険会社の担当者の中にも、十分に理解できていない方も見受けられます。
過失相殺が問題となるケースでは、どこまで差し引かれるかで金額がかなり変動しますので、よく確認することが重要です。
交通事故の被害遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
一家の支柱とは
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方が、加害者に損害賠償請求を行う場合に、一家の支柱であるかどうかによって金額が変わることがあります。
特に、交通事故の被害者の方が亡くなってしまった場合に問題となります。
死亡慰謝料は、裁判基準では以下の通りとされています。
・一家の支柱の場合 2800万円
・母親、配偶者の場合 2500万円
・その他 2000万円~2500万円
また、死亡逸失利益の算定においては、以下の算定方式が採用されています。
・基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
このうち、生活費控除率は以下の通りとされています。
・一家の支柱の場合
被扶養者一人の場合 40%
被扶養者二人の場合 30%
・女性の場合(主婦、独身、幼児等を含む) 30%
・男性の場合(独身、幼児等を含む) 50%
2 一家の支柱とは
では、この一家の支柱とは、どういう場合に該当するのでしょうか。
一般的には、一家の支柱とは、その者の収入を主として世帯の生計を維持している者のことをいいます。
典型的には、配偶者がいて、子供を扶養しているような家庭です。
では、子供が独立した家庭の場合にはどうでしょうか。
高齢の場合で、年金生活者であっても、その者の収入を主として生計を維持しているケースでは、一家の支柱と認定された裁判例があります。
その世帯での収入を検討して、被害に遭った方の収入がどのくらいの割合を占めているかが重要であろうと思われます。
3 まとめ
交通事故の被害に遭われ、特に、ご家族を亡くされてしまった場合、精神的なショックは大変大きいものと思います。
そのような中で、保険会社と示談交渉を行うことは、さらに負担が大きいと思います。
保険会社の提案が正しいのか、不安もあると思います。
お困りの際には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
可動域制限と測定方法
1 はじめに
前回と同様、今回も、後遺障害申請についてお話します。
おさらいですが、交通事故の被害者の方が、後遺障害の申請に当たっては、相当程度の通院を継続し、症状固定となった後に、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。その後、調査事務所で判断がなされます。
労災の場合と異なり、一部を除いて面談等が実施されることはありませんので、交通事故の場合には、この後遺障害診断書の内容が重要であることは、このコラムの中でも何度もお伝えしてきました。
2 可動域制限
交通事故の被害に遭われた方の中でも、むちうちと並んで多く見受けるのが、整形外科領域の可動域制限です。
特に骨折された方の場合、この可動域制限が一番と言っていいほど問題となると思います。
さて、この可動域制限ですが、正常値と比較して、どの程度、可動域が制限されたのか、多動値ないし自動値という数値を基に評価されます。
自動値は、対象者が、自力で関節を動かした場合の可動域のことをいいます。
他動値は、他人(主治医など)が、手を添えて関節を動かした場合のことを言います。
関節可動域の測定について、自動値と他動値の違いは、要は、自力で動かすか他人が動かすかという違いになります。
そして、関節可動域の測定は、後遺障害診断をするにあたっては、原則として他動値で判断することになります。
どのくらい可動域が制限されると何級と評価されるのかは、以下のページで明記しています。
4分の1制限されると12級
2分の1制限されると10級
というのが割合としては多い印象です。
3 測定方法
以上は、これまでの基礎知識をまとめました。
本日は、この後遺障害診断書を作成してもらうに当たって、注意が必要なケースを紹介します。
これまでお読みいただいた方には分かると思いますが、重要なのは後遺障害診断書にどのような数値が記載されているかです。
測定方法等が問題となります。
他動値の測り方について、測定する医師によっても、どこまで力を入れて測るかといった違いはあると思います。
それよりも重要なのは、どのようなシチュエーションで測るかです。
もちろん、これは、日常生活において、どの程度、可動域が制限されているかを測るものであるため、リハビリ治療等を受けていない、いわば「素」の状態の可動域が測られていなければなりません。
しかし、中には、リハビリ治療を受けた直後に、可動域の測定がされているケースもあります。これですと、交通事故の被害に遭われた方は、リハビリを受けて、筋肉の硬さもほぐれている状態で測定されていることになりますから、「素」の状態よりも可動域制限は緩和されている状態であると思います。
後遺障害の認定がなされるか、あるいは、より上位の認定がなされるか微妙なケースでは、このように、どのようなシチュエーションで測定されているかによって結論が変わってくる可能性があります。
最近、当事務所で依頼を受けたケースでは、上記のようにリハビリを受けた後に測定されていることから、「素」の状態より良い検査数値が出ていました。しかし、打ち合わせて事情をお聞きしたら、本来はもっと状態は悪いということでしたので、再度、リハビリをする前の状態で検査をしてもらいました。
おそらく、当初の検査数値では、後遺障害は認定されなかったのではないか、あるいは12級ではなく、神経症状として14級が認定されていたのではないかと思います。
4 まとめ
このように、交通事故の被害者の方が、適切な後遺障害の認定を受けるためには、相手方保険会社からの指示に従って主治医に診断書を作成してもらうだけでは不十分です。
特に可動域制限であれば、どのような測定方法で、どのような数値が出ているのか、あるいは、その可動域制限が生じた原因は何かまで掘り下げて検討する必要があります。
後遺障害の申請には、弁護士のアドバイスが重要です。
お困りの方は、是非、経験豊富な上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
通院に空白期間がある場合の後遺障害申請
1 はじめに
交通事故の被害者の方が、後遺障害の申請に当たっては、相当程度の通院を継続し、症状固定となった後に、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。その後、調査事務所で判断がなされます。
労災の場合と異なり、一部を除いて面談等が実施されることはありませんので、交通事故の場合には、この後遺障害診断書の内容が重要であることは、このコラムの中でも何度もお伝えしてきました。
本日は、この後遺障害診断書を作成してもらい当たって、注意が必要なケースを紹介します。
2 整骨院治療がほとんどの場合
交通事故の被害に遭われた方の中には、日中に整形外科に通院できる時間的な余裕がなく、整骨院治療をメインにされている方もたくさんいらっしゃると思います。
整骨院治療については、保険会社の打ち切りが早いことや、後から治療費の相当性等が争われる可能性があることは、これまでコラムに記載してきました。
しかし、もう1点重要なこととして、後遺障害診断書を主治医に作成してもらう際のことがあります。
もちろん、整骨院では、後遺障害診断書を作成してもらえることはありませんし、基本的には、整形外科の主治医と整骨院が、患者の症状を密に共有しているということも無いと思います。
そのため、あまりに整形外科への通院に感覚が空いていると、主治医に後遺障害診断書の作成をお願いした際に、作成を渋られたり、詳細な内容の後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。
このようなリスクもあるので、定期的な整形外科への通院は重要な問題です。
3 診療科目が異なる病院に通院している場合
また、事故により、複数の部位に傷害を負うということもあると思います。
例えば、骨折は整形外科、頭部は脳神経外科、肺は呼吸器外科といった形で、診療科目毎に分かれて診察を受けている場合、複数の病院に通院されているというころが起こります。
この場合、特定の診療科目については、長期間通院しないまま症状固定になるということもあります。
当事務所で最近担当したケースでは、事故直後は総合病院で、骨折や肺について診察を受けていたが、退院後は骨折の予後やリハビリを別の整形外科の病院に通院して行っていたということがありました。
しかし、依頼者の方は、肺についても強い違和感をお持ちでした。
骨折について症状固定になった後、現在通院していた病院に全体の後遺障害診断書の作成を依頼しましたが、肺については専門外ということで、当初の総合病院に依頼することを勧められました。
ただ、総合病院については長く通院をしていなかったため、肺だけの後遺障害診断書の作成を依頼しても、経緯が分からなかったと思われます。
そのため、当事務所の弁護士が同席させていただき、医師に経緯や事情を説明の上、再度の検査を実施してもらい、後遺障害診断書を作成してもらいました。
結果として、肺の部位の後遺障害が上位等級となって後遺障害が認定されました。
もし、弁護士に依頼していなかった場合、整形外科に肺に関する後遺障害診断書の作成を断られた場合、総合病院で改めて取り付けることを諦めてしまったかもしれませんし、総合病院に上手く経緯を伝えられなかったものと思います。
4 まとめ
以上のように、交通事故の被害者の方にとって、後遺障害診断書は、後遺障害認定にとって非常に重要な意味を持ちます。
依頼をされる医師の側にも、経験の差がありますし(医師としての診察の経験ではなく、交通事故の後遺障害診断書の作成においてという意味です)、空白のあるケースでは、弁護士が間に入ることでスムーズに行くことがあります。
交通事故の被害に遭われ、後遺障害申請を検討されている方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
交通事故と刑事事件③
1 はじめに
前回のコラムでは、刑事事件の流れをメインに記載しました。
刑事事件は、主に加害者が被害者あるいは被告人となって手続にどう関与するかという点が中心でした。
今回は、この刑事事件が、交通事故の被害に遭った方の側から見たときに、保険会社との示談交渉等にどのように絡むのかという観点から記載していきたいと思います。
2 民事の示談交渉の開始時期
まず、刑事事件については、在宅事件と身柄事件に分かれますが、交通事故案件の場合、在宅事件が圧倒的に多いことは前回お伝えしました。
事故後に、警察は、実況見分調書を作成しており、被害者、加害者、あるいは目撃者等の供述調書も作成しています。
これら捜査機関の手元にある書類については、刑事事件の処分が決まらないと、原則開示してもらえません。不起訴の場合には、実況見分調書のみ、有罪判決が確定すれば、検察官が刑事事件で証拠として提出したものは、開示を受けられます。
すなわち、在宅事件の場合には、不起訴であっても起訴されて有罪となった場合であっても、これらの書類の取り付けに時間が掛かるということです。
加害者の保険会社側もですが、警察の作成した実況見分調書は、事故態様や過失割合の検討に当たって、重視しております。そのため、事故態様や過失割合に関し、お互いの言い分が異なる事案の場合には、刑事事件が終了しなければ、民事の示談交渉が進められないという状況になることがほとんどです。
追突等で0対100であることが明らかな事案に関していえば、必ずしも刑事事件を待つ必要な無いかもしれませんが、それでも、関係証拠の精査をしてから民事の交渉を進めるという対応をすることは多くなると思います。
3 時間が掛かるのは悪いことなのか
以上のように記載すると、時間ばかり掛かって良いことは無いように思えてきます。
しかし、警察や検察の捜査に時間が掛かるというのは、それだけ重大な事故になっているケースが多いと思います。そうであれば、時間を掛けてでも慎重に対応するというのは必要なことだと思われます。
また、交通事故の被害者の方の損害賠償請求は、事故から完済までの間、年3%の割合による遅延損害金が付されます(2020年4月の改正前は年5%でした)。
したがって、事故から年月が掛かれば、それだけ損害賠償金に加算されていきますので、例えば、事故から3年が経てば9%が加算されることになり、もともとの損害賠償金が大きければ、付加される遅延損害金額も大きくなります。
以前のコラムで、示談交渉や裁判になった際の遅延損害金の一般的な扱われ方は記載しました。
示談交渉の場では、保険会社は一切負担しないですが、事故から長期間が経過している場合には、裁判になると遅延損害金が問題となることは保険会社も分かっていますので、その分、慰謝料等の額を裁判基準に近づけて解決しようという姿勢になることもあります。
裁判になれば、調整金名目で考慮されることが多くなりますし、事故から長期間が経過していれば、なおさらです。
4 まとめ
本日は、交通事故の被害に遭われた方から見た、刑事事件と示談交渉の絡みと、時間が掛かってしまうことの意味について、書かせていただきました。
上山法律事務所では、刑事事件の絡む交通事故の案件も多く扱ってきましたので、これらの経験を踏まえて、被害者の方のサポートをすることができます。
お困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
交通事故と刑事事件②
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた場合、警察に事故の連絡をして、現場の確認をすることになります。
物損の場合には、物件事故報告書が、人損の場合には、実況見分調書を作成することは、以前のコラム
で記載しました。
刑事事件との絡みで見ると、物損事故の場合には、加害者が罰せられることはありません(器物損壊罪は、故意=わざと壊した場合にのみ成立します)。
人損事故の場合には、加害者が被疑者となって捜査が進んでいくことになります。
本日は、刑事事件の流れをご説明します。
2 刑事事件の流れ
まず、刑事事件として裁判にかけるかどうかは、日本の法律では、検察官が判断することになっています。
交通事故の被害者の方のお怪我の程度がそれほどでもない場合には、警察は、微罪処分として検察に送らないで終わることもあるかもしれません。
検察に事件を送る場合には、書類送検という言葉と身柄送検という言葉があります。
書類送検は、加害者=被疑者の方を逮捕勾留することなく、在宅事件として扱う場合です。逆に逮捕勾留されている場合には、身柄を確保した状態で検察に送っているので、身柄送検という言い方になります。
その後の手続の流れですが、警察や検察の捜査の結果、最終的に検察が起訴(裁判にかけるかどうか)を決めます。
身柄送検されている事件の場合には、勾留期間が原則10日間、事情があれば一度だけ延長ができてもう10日の最大20日の間に捜査を済ませて起訴するかどうかを決めます(逮捕から勾留まで72時間の制約があり、逮捕時点からすると、最大23日ということになります)。
一方、在宅事件の場合には、この期間の制約がありません。検察官が、事件から裁判にかけるまでに公訴時効という概念があるのですが、この期間内であればよいということになります。参考までに、過失運失致傷罪(ケガをさせてしまった場合)の場合には5年、過失運転致死罪(死亡させてしまった場合)の場合には10年が公訴時効となっています。
交通事故案件の場合、被害者の方が死亡した事件であっても、逮捕勾留されていない事案はよく見かけます。お怪我の案件であればなおさらです。
上山法律事務所では刑事事件も扱っており、弁護人として交通事故の加害者側の刑事事件にも関与していますが、在宅事件が圧倒的に多いです。
したがって、刑事事件という観点からみると、警察や検察の捜査にかなり時間が掛かる案件が多いということになります。
交通事故の被害者の方が骨折した場合で、事故から半年以上経過していたり、1年くらいかかっているケースもざらにあります。
捜査が終了すると、検察が処分を決めます。不起訴にする場合もありますが、起訴する場合には、通常の公開法廷での裁判にかける場合と、略式起訴といって、罰金を言い渡す簡単な裁判手続にかける場合もあります。
私どもの刑事事件の経験からすると、交通事故の被害者の方が骨折等を負っている場合には、事故の予見可能性に疑義があるような事件でない限り、正式裁判にかかって、執行猶予付きの判決になるケースが多いと思います。死亡事故の場合にも同様で、実刑判決になるのは特殊要因があるような事案だと思います。
3 被害者の関与
では、上記刑事事件に、被害者はどのような形で関与するのでしょうか。
実況見分への立会を求められることもありますし、警察や検察官から、被害者として事故の状況や被害感情を確認され、供述調書の作成協力を求められます。
裁判のなった場合には、事案によっては検察官の側の証人として出廷し、証言の協力を求められることもあります。
被害者として公判に参加して意見を述べることもできます(被害者参加といいます)。
4 まとめ
交通事故の被害に遭われた方が、刑事事件として警察や検察に協力を求められた場合、民事事件の示談にどう影響するのかといったことも頭をよぎると思います。
上山法律事務所では、刑事事件の弁護人の経験も踏まえて、交通事故の被害者の方のサポートをすることができます。
お困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
保険会社によって、示談交渉に違いはあるのか
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、お怪我や物損の修理はもちろんですが、相手方の保険会社から適切な示談金を支払ってもらうことが重要です。
これまで、特に、過失割合が問題となる事案の場合等は、人身傷害補償保険を利用すること、つまり、ご自身の加入する保険会社に請求することも重要であることをお伝えしましたが、基本は、相手方の保険会社から支払ってもらうことになると思います。
では、この相手方の保険会社の示談交渉における対応について、保険会社毎に違いはあるのでしょうか。
結論から言うと、違いはあると思います。
2 どんな違いがあるか
(1)一般に、どの保険会社も、整骨院の治療に非常にシビアなところがありますが、ある保険会社は事故から3か月が経過すると一切認めない等といった形で、傾向があると思います。
(2)また、保険会社は、示談の提案をする際に、自賠責の基準を下回った提案をしてはいけないことになっていますが、交通事故の被害者の方に弁護士が付いていないと、自賠責の基準とほとんど同じような提案をしてくることがあります。
その方は、弁護士特約に加入されていなかったのですが、実際に、当事務所が相談を受けて、裁判基準等をご説明し、できるところまで一人対応していただくようアドバイスをしたのですが、当該保険会社からは、「弁護士が付かないならこれ以上は示談金の額は上がらない」等という趣旨不明な理由で対応してきました。実際に私どもが依頼を受けたら、相当額の金額の上乗せがありました。
その方は大変お怒りでしたが、当然だと思われます。当該保険会社の提案内容や姿勢は、その件だけに限られないものでした。
(3)他にも、とある保険会社は、慰謝料や主婦の休業損害がかなり低く見積もられており、当事務所が相談を受けて対応したところ、すぐに倍以上の提示をしてきたということもありました。その保険会社もまた、そのような対応が複数回見られています。
(4)一方、弁護士が付いていても、訴訟外の示談交渉の場面では、どの保険会社も、裁判基準の満額の支払いはしてくれません。
特に慰謝料について、8割から9割くらいの間で話し合いを付けることが多い傾向にあります。
ここの支払いについても、保険会社によって、訴訟外で認める幅が広い会社と狭い会社の傾向があると思っています。
3 まとめ
以上のように、実名は出せませんが、私どもは、保険会社による傾向の違いは間違いなくあると思っています。
そのため、当事務所では、交通事故の被害者の方からご依頼を受ける際には、相手方の保険会社がどこの会社か、場合によっては、その担当者が誰かについても関心を持っています。担当者は、物損担当と人損担当で分かれていることが多く、過去にスムーズに行った担当者なのかどうかについては、結構、関心を持っています。
当事務所では、某保険会社が相手方になったときには、示談で満足の行く解決ができない可能性が高いことから、速やかに訴訟提起の方針をとり、現に訴訟率が高くなっているといったこともあります。
このように、保険会社毎の特色もある程度把握しておりますので、相談初期からそのことをお伝えできる範囲でお伝えし、その後の方針を決めることに活かしています。
少しでもお役に立ちたいと思いますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。