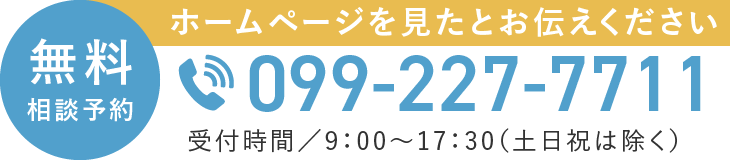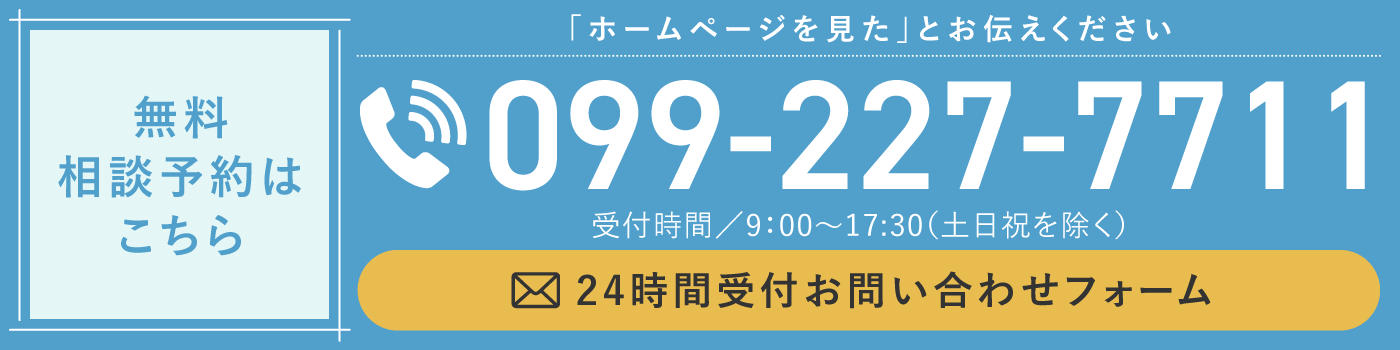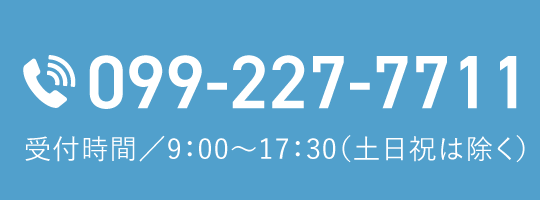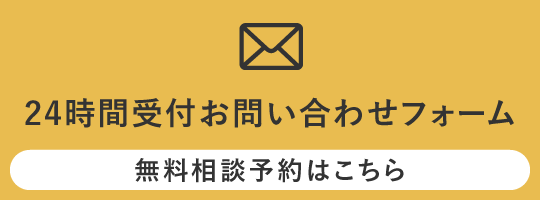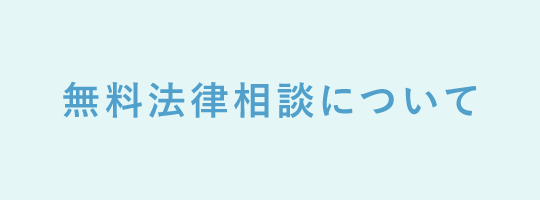Author Archive
弁護士費用と遅延損害金
1 はじめに
交通事故の被害者にとって、適正な損害賠償を受けることは非常に重要です。
損害賠償の項目については、治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)といったものが典型的で、これらについては、何となく聞いたことがあったり、イメージがしやすいと思います。
症状固定によって(事案によっては後遺障害認定の後)、損害が確定し、保険会社と示談交渉に入ります。
その際、保険会社も、上記損害項目については、裁判基準に照らして満額を支払うかは別ですが、交渉の土俵には挙げてきます。
しかし、保険会社は、弁護士費用と遅延損害金という項目については、示談交渉の段階では一切応じないのが通例です。
2 弁護士費用とは
一般に、日本では、紛争解決のために弁護士を選任することが強制されているわけではありません。そのため、ご自身が依頼された弁護士の費用は、ご自身で負担するのが原則です。
しかし、交通事故や医療過誤といった事故を原因とした損害賠償請求(不法行為に基づく損害賠償請求)の場合、実務的には、請求額に10%の弁護士費用を上乗せして請求することが広く行われています。
正確には、訴訟を提起した段階では、原告(被害者)側が請求額の10%を上乗せしますが、裁判所は、判決で認容した額の10%を認めることが多いです。
交通事故の場合、弁護士特約という商品が普及しており、これを利用したとしても同様です。
しかし、示談交渉の段階では、保険会社がこの損害項目を負担することはまずありません。
裁判になると、一般的には、裁判官は和解による解決を探るものですが、和解の段階では、後述する遅延損害金と合わせて、調整金という名目で一定程度を上乗せすることは行われていますが、10%を認めるのは、和解ができずに判決に至った場合が基本になります。
3 遅延損害金とは
一般に、交通事故等の不法行為に基づく損害賠償請求の場合、不法行為の日(事故の日)から損害賠償請求権が発生し、遅滞に陥っている考え方が取られています。
そのため、賠償額の全額が支払われるまで、元金に対する遅延損害金が発生しています。2020年4月以前の事故の場合には年利5%、同月以降は年利3%です。
加害者が事故に誠実に向き合わずに放置した場合はもちろんですが、保険会社との示談交渉が長引いているといった理由を問わず、損害賠償がなされていなければ、遅延損害金は発生しています。
しかし、これも示談交渉の段階では、保険会社は一切負担しません。
裁判になった場合の扱いは、弁護士費用と同じように、和解の段階では調整金名目で、判決になった場合には満額認められるという処理が基本になります。
4 どうすべきか
弁護士費用と遅延損害金について、保険会社が示談交渉の段階では一切認めないことは既にお伝えしました。
しかし、これは見過ごせない損害項目です。たとえば、事故から1年経過していれば、13%上乗せになります。改正前の事故で、事故から3年が経過していれば25%上乗せになります。
もちろん、これら満額が認められるのは、和解ができず判決に至った場合ですが、和解の段階でも一定程度は考慮されますし、もともとの損害額が大きければ、考慮される額も大きくなります。
したがって、後遺障害が残存したケースや、死亡事故の場合等の、損害額が大きくなる事故の場合には、弁護士費用と遅延損害金の上乗せを検討して方針を決めることになると思います。
意外と知られていない問題だと思いますので、交通事故の被害者の方は、是非、頭に入れておいていただけましたらと思います。
上山法律事務所では、損害賠償の回収可能額の見込みを踏まえて、最適な方針を提案するよう努めております。交通事故でお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
相手方が無保険の場合
1 はじめに
交通事故の被害に遭い、相手方が無保険だった場合、皆様はどうしますか。まずは、被害に巻き込まれた上に、加入すべき保険に加入せず、正当な賠償を受けられないのではないかという不安や憤りを覚えるのではないでしょうか。
被害者として当然のことと思います。
本日は、当HP内の「無保険の加害者と事故に遭ったら」(https://kagoshima-koutsujiko.com/muhoken/)について、当事務所で経験談を踏まえて、詳しく書いていきたいと思います。
相手方が無保険というのは、強制保険(自賠責)に加入していないケースと、自賠責には加入しているけれど、任意保険に加入していないケースというのがあり得ます。
前者の強制保険(自賠責)に加入していないケースの場合、人損の部分に関しては、政府保証事業制度というものを利用して、自賠責と同様の補償を受けられる可能性があります。しかし、そうであっても、後者の任意保険に加入していないケースと同様に、上乗せ部分についての補償が受けられない可能性があります。
以下では、相手方が任意保険に加入していない場合ということでお話を進めます。
2 相手方が任意保険に加入していない場合
相手方の自賠責(あるいは政府保証事業制度)から回収できなかった部分については、相手方と直接交渉して支払ってもらうよう働きかけるのが原則的な対応になります。
しかし、相手方に支払能力が無く、治療費の支払いすら期待できそうにないケースや、途中から加害者と連絡が取れなくなったということで弁護士の下に相談に来られるケースもあります。
そのような場合、人身傷害補償保険の活用を検討してみる価値があります。
3 人身傷害補償保険の活用
人身傷害補償保険については、令和4年7月29日のコラムでも色々と書かせていただきました。特に、この商品の存在によって、過失相殺の結果に拘らずに進めることができる可能性があることをお伝え致しました。
しかし、人身傷害補償保険にはもう一つ良い点があります。
交通事故の損害賠償は、相手方の保険会社と交渉して回収するのをイメージされる方が多いと思いますが、ご自身が人身傷害補償保険に加入している場合には、ご自身の保険会社に連絡をして支払ってもらうこともできます。
この人身傷害補償保険ですが、一般に上限を3000万円と5000万円で設定されているケースを多く見ます。ただ、相手方が無保険の場合には上限を撤廃して無制限になるという対応をしている保険会社も存在します。
私どもが経験した事例では、被害者には高次脳機能障害により重度の後遺症が残りましたが、加害者が任意保険に加入していなかったというものがありました。その事例では、被害者の人身傷害補償保険を利用し、7000万円近く保険金を支払ってもらいました。
また、人身傷害補償保険は、ご家族が加入する保険で利用ができたり、歩行中の交通事故でも利用できる可能性があります。先ほどの私どもが経験した事例では、被害者ご自身は人身傷害補償保険には加入していませんでしたが、奥様が加入しており、それを利用して保険金を受け取ることができました。
このように、見落とされる可能性がある一方で、利用できるのとできないのでは天と地ほどの差があります。
相手方が無保険の場合であっても、諦めずに知恵を絞ることが重要です。一緒に解決策を考えますので、上山法律事務所にご相談ください。
4 物損の場合
なお、物損事故の場合、残念ながら、人身障害補償保険は利用できないので、ご自身が車両保険に加入していない場合には、無保険の相手方と直接交渉をしなければなりませんので、ご注意ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
交通事故と刑事事件
1 交通事故の発生と警察への報告義務
交通事故が発生すると、道路交通法上、警察への報告義務があります(これをしないと3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります)。
警察に事故を報告すると、警察が事故現場に訪れて、事故状況を確認します。
警察が作成する事故状況に関する報告書は、交通事故の被害者にとって、今後の交渉や裁判において、非常に重要な意味を持つことがあります(特に、過失割合が争われるケースで重要です)。
2 物損事故の場合
物損事故の場合は、物件事故報告書という簡単な事故状況の図面を作成して終了します。これは事故の詳細までを明らかにしたものではない簡易なものではありますが、それでも、事故態様の一部が明らかになることはあります。
過失割合が問題となるケースは、私どもの感覚では、物損事故の方が多い印象です。
保険会社が間に入ると、以前、このコラムの「物件事故について」でも記載したように、保険会社は、加害者から事情を直接聴き取りすることなく示談交渉を進めるケースもあります。その場合に、事故当時に加害者と確認したことを、後から保険会社が大きく覆した場合に、証拠として使える場合もあります。
3 人身事故の場合
より重要なのは、人身事故の場合です。この場合には、警察が実況見分調書という書類を作成します。
双方が立ち会って、認識の相違なく作成されればよいのですが、必ずしもそうなっていないケースがあります。
例えば、被害者が重症ですぐに病院に運ばれて入院することになってしまったケース等では、加害者のみ事故現場に立ち会う形で、加害者の認識を前提に実況見分調書が作成されてしまうことがあります。
保険会社は、基本的にはこの実況見分調書を前提に過失相殺を検討することになるため、交通事故の被害者側の認識と異なる場合に、覆すことが難しくなります。
そのため、当事務所では、交通事故発生の初期からご依頼をいただき、実況見分が実施される際に、被害者の代理人として、被害者と共に現場に立ち会うといったことも行ってきました。民間の交通事故鑑定会社に依頼をして、実況見分調書の事故態様はおかしいと主張し、当方の認識する事故態様に近い形で裁判所から事実認定を受けることができた事案もあります。
4 まとめ
交通事故の被害に遭われた方は、事故直後から不安な毎日を過ごされていると思います。
警察への対応、保険会社への対応と分からないことばかりではないでしょうか。
特に、過失割合が0対100ではないケースの場合には、今後の過失相殺の検討に当たって、事故状況・事故態様が正確に把握されることは非常に重要です。
上山法律事務所では、事故直後から、あらゆるアドバイスができる体制を整えておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、ご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
症状固定の適切なタイミング
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方で、後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定手続を行う必要があります。
その前提として、症状固定とされた後に、主治医から後遺障害診断書を作成してもらわないといけません。
後遺障害の認定手続のバリエーションについては、このコラムで以前記載していますが、今回は、その前段階のことをお話します。
2 一般的な症状固定時期
一般に、事故によってむち打ち症となった場合には、2~3か月くらいで保険会社が治療費を打ち切るという話が出てきますが、後遺障害の等級認定を勝ち取るためには、6か月程度の通院実績が必要であると言われています。
骨折の場合、状態にもよりますが、これまでの私どもの経験で行きますと、ボルトを入れて抜去するような事案であると、ボルトを抜いてリハビリを経て、概ね1年程度で症状固定になり、そうでないケースの場合は6カ月から1年くらいの印象です。
脳の障害の場合には、1年から1年半程度、症状によってはさらに長期間を経て症状固定となっていると思われます。
これらは目安ではありますが、症状固定までの期間は、治療費を損害として請求できる可能性が高く、症状固定後の治療費は原則として請求ができないという棲み分けの意味でも、症状固定時期は重要です。
3 症状固定時期は遅らせた方がよい?
では、症状固定時期は、できる限り遅らせた方が有利なのでしょうか。
後遺障害の等級認定に当たっては、医師の作成した後遺障害診断書と画像を踏まえて判断されます。労災の場合は面談等をして地方医がもう少し丁寧に判断しますが、自賠責の場合は、書面審査が一般的です。
したがって、この後遺障害診断書にどのように書かれるかがポイントになります。
定期的に通院している場合、患者の側から症状固定時期について希望を伝えると、主治医の先生も親身に検討してくれることは多いのではないでしょうか。
しかし、症状固定時期を遅らせた結果、リハビリ効果が出て、症状が良くなるということはあり得ます。そうすると、例えば、可動域の制限が問題となるようなケースの場合、ある時期に症状固定と判断されていれば後遺障害が認定されていた可能性、あるいは、より上位の等級が認定されていた可能性があるのに、症状固定時期を長くした結果、後遺障害が認定されなかった、あるいは、下位の等級が認定されてしまったということが生じ得ます。
もちろん、交通事故の被害者の方からすれば、お体の具体が良くなったということなので、それはそれで喜ばしいことなのですが、賠償の観点からすれば、損をしているという見方もできます。症状固定という言葉が、医学的には症状の改善がない状態という意味であるとすれば、先ほどの「ある時期」の例は、まだ症状固定ではない時期であったともいえるかもしれません。
しかし、タイミングによっては上記のような差異が生じる可能性があることは、頭に入れなければなりません。
4 まとめ
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方の症状を定期的に把握し、どの時点で後遺障害の申請に入るか、症状固定のタイミングもアドバイスします。
後遺障害診断書の作成に当たっては、主治医とのコミュニケーションを図る努力もしています(面談をお願いしたり、後遺障害診断書作成に当たって着目して欲しい点について、お手紙を送付したりしています)。
交通事故の被害に遭われ、後遺障害認定を考えていらっしゃる方は、是非、一度、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
弁護士特約の範囲
1 弁護士特約とは
弁護士特約は、交通事故の被害者にとって、弁護士への依頼のハードルを下げるとても大事な商品です。
現在、普及率はかなり高いと思いますが、時折、明らかに弁護士が介入すべき事案であるのに、弁護士特約に加入していないために及び腰になってしまっている方をお見受けします。毎月の保険料にすれば多額でも無いため、是非加入を推奨したい商品です。
さて、この弁護士特約ですが、弁護士報酬の上限は300万円となっています。大半はこの範囲内で賄えるであろうと思います。当事務所で弁護士特約を超える案件は記憶にありません。
2 弁護士特約の適用範囲
また、本来使えるはずであったのにそれに気づかないということもありうると思います。
弁護士特約の適用範囲について、各保険会社の約款を確認する必要はありますが、概ね以下の通りとしている保険会社が多いのではないでしょうか。
① 契約者(被保険者)本人
② 契約者(被保険者)の配偶者
③ 契約者(被保険者)の同居の親族
(例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族
④ 契約者(被保険者)の別居未婚の子
(例)実家を出て暮らしている結婚していない子ども
⑤ 契約車に搭乗中の者
⑥ 契約車の所有者
要するに、自分が加入している保険でなくても使える場合があるのです。
そのため、当事務所では、法律相談をお受けした際に、ご自身が弁護士特約に加入していないというケースであっても、必ず、ご家族等の加入状況も確認するようにしています。
交通事故の被害者の方にとって、弁護士特約を利用できるかは、適切な損害賠償を受け取ることができるかという点からも非常に重要な問題です。
そのため、まずは、ご家族の加入状況等も忘れずに確認されてみてください。
上山法律事務所では、弁護士特約加入の有無を問わず、交通事故の相談は無料としていますので、まずはお気軽にご相談ください。私どもの方で弁護士特約の利用の可否を調査することも可能です。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
後遺障害の認定について
1 後遺障害認定手続の種類
交通事故の被害者が、治療を継続した結果、症状固定となり後遺障害が残った場合、後遺障害の申 請及び認定については、以下の方法があります。
① 自ら自賠責に被害者請求を行う
② 相手方保険会社に事前認定手続きをとってもらう
③ 自らが加入する人身障害補償保険に事前認定手続きをとってもらう
これら3つの方法は手続の仕方の差異であり、自賠責調査事務所が後遺障害の認定を行います(JAだけは別の組織を持っていますが、JAの方が一番判断が厳しい印象です)。
これら3つの方法を比較すると、①については、必要書類を自分で収集する手間がありますが、自分の提出したい書類で判断してもらえます。②③については、保険会社側が大半の資料を揃えるので、何を提出されたかが分からないという問題があります。時に、保険会社側が被害者に不利な意見書を付けて提出しているのではないかという話もあります(私どもの方で、この点を保険会社に確認したことがありますが、その際、保険会社は、よほどのことが無い限り、そのようなことはないという言い方でした…)
後遺障害の認定という問題で言えば、どの方法をとっても結論は変わらないという意見もあれば、やはり被害者請求の方がいいのではないかという意見もあります。当事務所としては、それよりも後遺障害診断書の出来が重要と考えておりまして、実際にどの方法をとっても大差は無いと考えています(特に、整形外科の領域(可動域制限等)が問題となる事案では、後遺障害診断書に数字で記載されますので、動かしようがないと思います)。
2 労災
さて、上記で述べたことは一般的な交通事故の案件の場合です。
交通事故の被害者に遭われた方が、勤務中であったり、通勤中であった場合、労災が利用できる場合があります。その場合には、労災に後遺障害の申請を行うこともできます。
一般論としてですが、労災の後遺障害認定は、自賠責調査事務所よりも後遺障害認定については緩やかな印象があります。特に、審査についても丁寧で、自賠責調査事務所の場合は、いわゆる醜状障害と言われる後遺障害が問題となる場合には面談を行いますが、それ以外では面談はありません。
労災の場合、原則、地方医と呼ばれる労災担当の医師と面談があります。また、治療経過や症状についても、詳細に調査がなれています。
3 どちらの手続きを使ったらいいか
以上のような事情があるため、当事務所では、交通事故の被害者の方で、労災が利用できる事案の場合、まずは労災から後遺障害認定を得るようにしています。
ただ、保険会社は、交通事故事案の場合には、労災の認定だけでは示談交渉に応じず、調査事務所の結果を経てから交渉に臨むという姿勢をとってきます。
そのため、労災を経由する分、どうしても交渉に入るまでに時間が掛かってしまいます。
ただ、労災の認定結果の資料を自賠責調査事務所にも使えるため、自賠責でも同様の判断をしてもらえる可能性は高まると思います。
先日、労災で後遺障害12級の認定を得ていたのですが、自賠責では14級という方の依頼を受けました。自賠責では、労災で利用した資料の全てを提出していたわけではないため、当事務所で異議申し立てを行ったところ、自賠責も異議が認められて12級となりました。
4 それでも労災はメリットがある
ただ、結果として、労災と自賠責で異なる判断が出てしまう可能性もあります。その場合、裁判所は、自賠責の判断を優先する傾向があります。
理由は様々あるのですが、労災が明確な根拠を示さずに自賠責より上位等級を認定していると判断 している場合が多いのではないかと思っています。
では、結果的に裁判所が自賠責を優先するなら、このような労災を経由してから自賠責に後遺障害申請を行うという手順が無駄なのかというと、そうでありません。
労災の場合、後遺障害が認定された場合には、特別支給金というものが支給されます(休業補償給付や遺族補償給付でも同様です)。
これは、損害賠償の場面では損益相殺の対象になりません。したがって、これらの支給金は、実際に加害者に損害賠償をする際には差し引きされずに丸まるもらえることができることになります。
まとめると、労災が利用できる事案では、後遺障害がより上位の等級になる余地があること、特別支給金を得られることがから、労災に後遺障害の申請を行うことをお勧めしています。
これらは非常に専門的なお話になりますので、交通事故の被害に遭われた方で、後遺障害認定を考えていらっしゃる方は、是非、上山法律事務所にお問い合わせください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
物損事故について
物損事故は、人身事故に比べると、損害額は低いですが、実は訴訟になる可能性は同じくらいあります。物損事故で主に問題になるのは、①修理費、②過失相殺です。
1 ①修理費について
修理費は、加害者側の保険会社のアジャスター(交通事故が起きた際、保険会社から委託を受けて自動車の損傷状態を調査し、損害額の認定を行う専門家)と、被害者が車両を持ち込んだ工場とで協定というものを交わして進めますので、修理費自体で揉めるケースは必ずしも多くはありません(衝突部位から言って、ここまで故障するはずはないといった形で争いになるケースが無い訳ではありませんが)。
修理費は協定で決まったとしても、経済的全損(修理はできるけれども修理費用が車の時価額を上回った場合)に当たると、保険会社は修理費の全てを賠償はしてくれません。この場合、損害額=車両の時価相当額+買い替え諸費用ということになります。
車両の時価相当額については、レッドブックと言われる本を参考にしたり、中古車市場で実際に売却に出ているものを参考にしたり、様々検討するのですが、簡単には合意に至れないことが多いです。
また、買替諸費用(登録費用、消費税等といった買い替えの際の経費です)について、示談交渉の段階では一切支払わないと言ってくる保険会社もあり、そのような保険会社の対応に不満を抱き、結局は裁判を選択するということがあります。
2 ②過失相殺について
②過失相殺については、人身事故以上に争いになることが多い印象があります。
人身事故の場合、以前コラムで記載した人身傷害補償保険が普及しているということもあり、裁判すれば、過失割合がどうなっても被害者が回収できる金額は変わらないという状況になっていますので、ある程度、被害者側も感情的にならずに解決できる途があります。
しかし、物損はそうは行きません。過失割合如何で、どちらが悪かったからという白黒をつけることになるため、追突といった0対100であることが明白な事故でない限り、簡単には合意に至らないことがままあります。ドライブレコーダーが無いケースでは、客観的な資料が乏しい場合も多く、その場合は困難事案となります。
特に、私ども弁護士の立場で疑問に思う保険会社の対応があります。例えば、加害者側が法人契約の保険で、従業員が仕事中に起こした事故であった場合や、保険代理人店経由で保険会社が事故の情報を収集している場合、示談交渉を行う加害者側保険会社の担当者は、運転者本人から事故情報の聴き取りをしていないことがあります(このようなケースは少なくない印象です)。そのため、事故直後に被害者と加害者が事故状況について確認した共通認識や、交わした会話が無視されたりして、被害者側が感情的になってしまうこともあります。事故の後、保険会社から連絡をもらい、事故直後の加害者側の主張が大きく変遷した件もあります。
このような保険会社の対応は改められるべきですが(少なくとも、弁護士であれば、依頼者本人から直接の事情の確認は必ず行います。保険会社が加害者側の代理人として対応するのであれば、担当者が運転者本人から事情を確認することは、当たり前に行われるべきことです)、このような対応をされた結果、感情的対立から裁判に至るということもままあります。
3 その他
上記では、①修理費(経済的全損を含む)、②過失割合について見てきましたが、他にもレンタカー代・代車使用料で揉めることもあります。
保険会社によっては、双方過失があるケースの場合には負担しないという主張をしてきたり、実際に修理していなければ負担しないといった主張をしてくることがあります。
前者は全く理屈が通らないです。レンタカーを使用する必要があるのであれば、過失割合に従って負担すべきは当然です。
後者についても、そもそも実際に損傷しているのであれば、修理をしなくても修理代は損害として発生していますし、修理をすることが義務ではない以上、その検討のために要した期間のレンタカー代は負担すべきです(同趣旨の裁判例もあります)。
他にも、代車を使用する期間が長期間だという主張がなされたりすることもあります。代車の使用期間については、裁判例も明確な基準が無いため判断に迷うケースもあります。
最近では、いきなり保険会社側が弁護士を立てて、一方的に期限を定め、そのときまでに代車を返さないと、以降は保険会社が負担しないという文書を送りつけられたというケースがありました。このような対応をされれば、被害者側としては頭に来ると思います。冷静な話し合いをする土俵を保険会社の側が崩していると言わざるを得ません。
4 最後に
長々と物損事故について記載しましたが、ある意味では人身事故の場合よりも保険会社の対応に不満を持たれる方も多く、裁判になる可能性は人身事故に比べても決して低いものではありません。
物損事故に遭われて対応に困っている方は、ぜひ、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
人身傷害補償保険について
1 自分の加入する保険会社 とも話ができる
交通事故の被害に遭われた方のほとんどは、加害者の加入する任意保険会社と交渉するものと考えていると思います。
しかし、自分の加入している保険会社に確認し、人身傷害補償保険という保険に入っている場合、ご自身の加入する保険会社から保険金を払ってもらえる可能性があります。
2 メリット
メリットとしては、人身傷害補償保険は、過失割合を問わない商品と言われており、相手方保険会社が過失割合等で争ってきてなかなか話し合いが付かない場合に、速やかに一定程度の保険金を確保できるという点が挙げられます。また、弁護士特約と同様に、人身傷害補償保険を利用しても、等級が下がって毎月の保険料が上がるということもありません。
3 注意点
ただ、注意も必要です。人身傷害補償保険を支払う保険会社は、人傷基準といって、自社基準に従って保険金額を算出し、支払います。裁判基準(弁護士基準)よりは低くなることがほとんどです。そのため、裁判基準(弁護士基準)で満額を回収しようと思ったら、やはり最終的には裁判をする必要が出てきます。
裁判をすると、人身傷害補償保険は、裁判基準(弁護士基準)に従って計算された損害額の中から、過失相殺で相手方から差し引かれる部分について支払ってもらえます(これは、相手に裁判をした後から人身傷害補償保険をもらう場合です)。先に人身傷害補償保険をもらってから、相手方に裁判をした場合は、裁判基準(弁護士基準)に従って計算された損害額の中から、まず、過失相殺で差し引かれる部分について充当された上で、その他の損害の一部に充てられたという計算をします。
4 まとめ
やや話が複雑になりましたが、結論としては、人身傷害補償保険を相手方に裁判する前にもらっても、後からもらっても、裁判基準(弁護士基準)で計算された損害から過失相殺で差し引かれた部分も全額回収できるということです。
その意味で、過失割合に拘る必要がなくなり、交通事故裁判で難しい争点の一つと言える過失相殺の問題が消えるというメリットがあります。逆に、過失相殺が問題となるケースでは、常に利用の要否を検討する必要がある商品です。
なお、ご自身が人身傷害補償保険に加入していなくても、ご家族が加入する保険で利用ができたり、歩行中の交通事故でも利用できる可能性があります。保険会社は、申請されなければ交通事故が発生したかどうか分からないため、調査はしません。そのため、結構見落とされているケースもあると思っています。
交通事故に遭われて、過失相殺が問題になる場合には、いつでも上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
整骨院治療について
交通事故の被害に遭われた方で、整骨院に通院される方も多いと思います。
整形外科に比べて遅い時間帯にも対応してくれる傾向もあることから、お仕事をされている方は、整形外科より整骨院の方が頻回に通院しているという案件もよく見受けられます。
しかし、注意が必要です。
整骨院への通院については、保険会社は抵抗を持っています。治療費の打ち切りが整形外科に比べて早まったりすることがあります。また、示談交渉の段階になって、保険会社の方が整骨院への通院の必要性を否定するケースもあります(訴訟の段階に至ると、この傾向は顕著です)。
一般に、整骨院治療は、以下の要件を満たす必要があるとされています。
1 医師の指示がある場合
医師の指示がある場合には、医師による治療の一環といえるからです。
2 医師の指示がない場合
医師の指示がない場合は、医師の指示があったと認められるのと同等の、以下の諸条件を満たす必 要があります。
➀ 施術を受ける必要性があること(整形外科での治療のほかに施術を受ける必要があったか)
② 施術の合理性があること(必要な部位に関して施術が行われたか)
③ 施術の相当性があること(怪我の程度に比して施術内容・期間・費用などが相当だったか)
④ 施術の有効性(施術によって具体的な効果が認められたか)
もっとも、上記1~4の条件が満たされた場合でも、全額の支払いを受けることができるのは稀で割合的な減額がされることもあります。
保険会社の方で、整骨院に費用を支払っていたら、それを容認していたのではないかと思われるかもしれません。しかし、裁判所はそのように認定はしてくれません。
整骨院での通院を継続する場合には、上記の要件を満たすかの確認が必要です。
また、整骨院の通院だけに偏るだけでなく、定期的な整形外科への通院と併用することをお勧め致します。整形外科への定期的な通院があれば、治療継続の必要性は認められやすくなりますし、後遺障害の申請を行う際にも、整形外科への定期的な通院が無いと、後遺障害診断書の作成をお願いする際に支障が出る可能性があります。
治療中の対応方法を間違えないことも重要です。事故に遭われて不安がありましたら、いつでも上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。