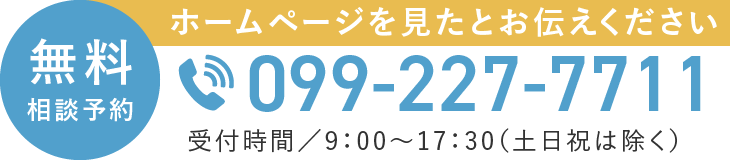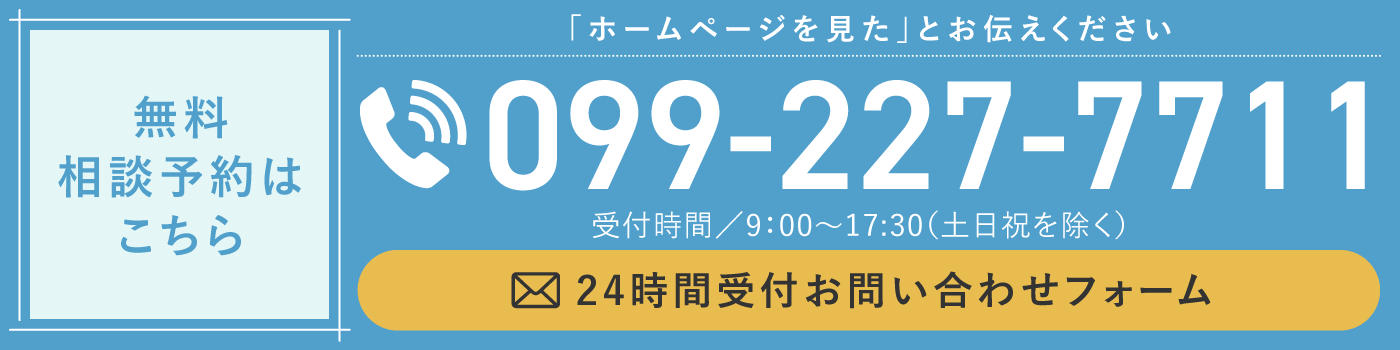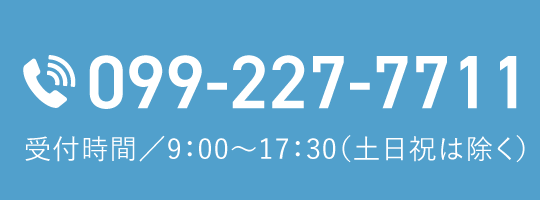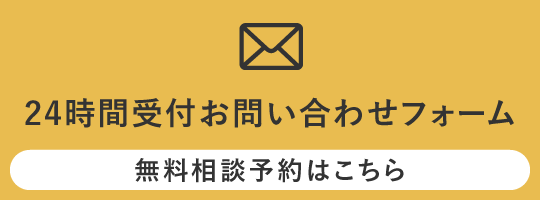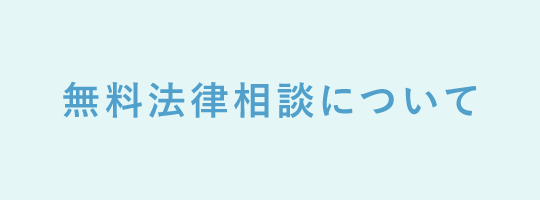Author Archive
バスとの事故
1 はじめに(バスとの事故について)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
今回は、相手方車両がバスのときのことを考えてみたいと思います。
2 基本的な示談交渉の進み方
バスが相手であっても、基本的な示談交渉の進み方は変わりません。
基本的には、バス会社の加入する保険会社が対人賠償という形で、示談代行をしてくると
思います。
損害の算出の方法も、基本は変わらないと思います。
過失相殺については、バスの運転手の場合に、普通免許の方と比べて、注意義務の程度が重くならないのかという考え方もありうるかもしれませんが、基本的には、裁判所が前提にしている判例タイムズ社の事故類型に照らして考えることになると思います(バスであることを重視するなら、その中の修正要素の中で、「著しい過失」に該当するかどうかという形で交渉することになると思います。)
3 示談交渉がまとまらないとき
公営バスが相手方の場合には、地方公共団体を被告として国家賠償請求をすることになると思います。
では、民間事業者が自治体等から業務委託を受けている場合、どうなるのでしょうか。
この場合も、基本的には地方公共団体を被告として国家賠償請求をすることになると思います。
先般、バス会社が民間事業者の事案の依頼を受けて示談した案件があります。
その際には、保険会社は、自治体が加入していた保険に対応する保険会社でした。結果は示談で終了しましたが、その保険会社の担当者と雑談でお話をした際、仮に訴訟になっていたとして、地方公共団体を被告当事者としていない場合には、その保険会社からは支払いができないだろうとのことでした。
ただ、通常の交通事故訴訟のような民事の損害賠償請求訴訟と、国家賠償請求訴訟でも、交通事故訴訟の場合には、大きな違いはありません。
過失相殺や損害額がメインとして争われていくと思います。
4 まとめ
以上見たように、基本的には、バスが相手でも、示談交渉の手順や考え方に大きな違いはありません。
上山法律事務所では、このような事案も実績がありますので、お困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
停車中の衝突事故について
1 はじめに(停車中の衝突事故について)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
今回は、自分が停車しているときに衝突された事故について、考えてみたいと思います。
最近、立て続けに相談があった事故類型になります。
2 過失割合の考え方
例えば、追突事故の場合、原則は100対0と言われています。
追突事故も、前方の車両が停車中に、後続の車両が衝突するというケースが多いと思います。
では、例えば、対向車がそのまま行違うには狭くて衝突しそうになり、片方の車両が少し道路から逸れて停車していたところ、反対側の車両が進行した結果、衝突したような場合はどうでしょうか。
通常、裁判では、過失割合は、別冊判例タイムズ38という書籍を参考にすることが多いです。この中で、似ている事故類型を確認し、基本割合を踏まえて、修正を加えるという手順で検討していきます。
しかし、ぴったりと当てはまらない事例も多いです。
3 停車中という事実はどう評価されるのか
今回のような、停車中の衝突事故の場合、衝突された被害者の側からすれば、事故は避けられないですし、停車しているところを衝突されたわけなので、過失割合は100対0ではないかと主張される方が多いです。
これは、私どもとしても、感覚的には当然のことなのかなと思っています(実際に、自分がそのような事故に遭えば、どうして自分に過失があると評価されるのか理解できないと思います)。
ところが、実際の示談交渉の現場や、裁判では、100対0という認定に持って行くのはかなり難しいのが実情です。
先の追突事案と異なるのは、追突事案は、基本的な過失割合がそもそも100対0であるとされているのに対し、先の例の停車中の衝突事故等は、基本が100対0とは考えられていないからです。
先ほどの、基本から修正を加えるという点についてですが、例えば、加害者側に著しい過失がある場合には、加害者の過失を10%加算する、重過失があると20%加算するといった形で処理していくことになります。
正解は私どもも分かりませんが、停車しているところに衝突したという事実は、これらの修正要素の中で考慮されるという考えになるのだと思っています。
したがって、これらの修正を加えてもなお、100対0にならない場合には、その主張は難しいという形になります。
4 まとめ
停車中に衝突された事故の場合、どうしても過失割合に納得ができないという方が多いと思います。
100対0の主張にハードルがあるのは事実ですが、追突事故でなくても、そもそもの事故類型に、修正を加えれば100対0になるという事案もあると思います。
上山法律事務所では、このような事案も多く扱っていますので、お困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
高齢者の逸失利益(年金)について
1 はじめに(高齢者の逸失利益(年金)について)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
死亡事故が発生した場合、被害者の相続人は悲しみに暮れる日を送ることになります。四十九日が明けると、相手方の保険会社も示談の提案をしてきます。
事案が事案なだけに、神妙な態度で提案をしてきますが、提案内容を確認しないままに印鑑を押していいのでしょうか。
高齢者の死亡事故の場合、給与収入や年金収入の逸失利益と死亡慰謝料が問題となります。
本日は、このうち、年金収入の逸失利益についてお話します。
死亡慰謝料については、以下の投稿があります。
2 年金の逸失利益性
年金の逸失利益性について、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の老齢年金,退職共済年金等の退職年金,障害基礎年金や障害厚生年金等の障害年金については,逸失利益性が肯定されますが,遺族厚生年金や軍人恩給の扶助料等の遺族年金については,逸失利益性が否定されます。
逸失利益性が認められる年金の計算式については、以下の通りです。
【年金年額×(1-生活費控除率※①) ×生存可能年数に対応するライプニッツ係数※②】
①の生活費控除率は、男性については30~50%程度(一家の支柱で30~40%、独身で50%程度)、女性については30%程度とされることが多いですが、年金生活者の場合は,年金収入に占める生活費の割合は高まるのが一般的なので,生活費控除率は50%~70%に引き上げられることが多いです。
②のライプニッツ係数は、例えば67歳を超える方の場合は、平均余命の2分の1とされていますが、年金の場合には2分の1の差し引きはありません。
このように、通例の死亡逸失利益と比べて、計算式がやや異なっているので、注意が必要です。
3 まとめ
以上のとおり、高齢者の方の逸失利益(年金)について述べてきました。
上山法律事務所では、死亡事故も多く対応してきておりますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
未成年者の事故と過失相殺②
1 はじめに(未成年者と過失相殺)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
交通事故の被害者がお子さん等の未成年者の場合、以下の投稿でも記載していますが、親権者が法定代理人として示談交渉を行うことになります。
2 被害者側の過失
前回、未成年者の過失相殺能力ということで、具体的には、5歳ないし6歳で事理弁識能力が備わると判断している裁判例が多くあることを投稿しました。
これは、被害者である未成年者自身の行為を過失相殺の対象にできるかという観点から問題になっています。
これとは別に、被害者側の過失というものがあります。
最高裁は、さらに次のような判断も示しました。すなわち、被害者本人に事理弁識能力がなくても、「被害者側」に過失があれば、過失相殺してよいというものです。「被害者側」とは、「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者」のことをいいます。例えば幼児の父母などです(上記最高裁の判例では、被害者である幼児を監督する立場にあった保育士の過失を被害者側の過失として評価することは否定されました)
この判断からすると、母親が目を離したすきに、一緒に歩いていた3歳の子が道路に飛び出して交通事故に遭った場合、母親の不注意があるとして過失相殺がされてしまう可能性があります。
3 まとめ
前回と同様に、未成年者が被害者に遭う交通事故の場合にも、過失相殺は問題になりえます。
子どもたちが交通事故に遭わないように、日ごろからのしつけは大変重要ですし、運転する側の注意もとても大事です。
ただ、子供が事故遭われた事例も経験がありますので、お困りの際には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
未成年者と過失相殺①
1 はじめに(未成年者と過失相殺)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
交通事故の被害者がお子さん等の未成年者の場合、以下の投稿でも記載していますが、親権者が法定代理人として示談交渉を行うことになります。
2 未成年者の過失相殺能力
上記で引用した以前の投稿でも、責任能力は、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能と定義されており、これまでの判例や裁判例を見る限り、大体12歳程度で責任能力があると判断されていることが多いです。
ただ、これは、未成年者が加害者の場合に、責任を問えるかという観点から議論されているものです。
いわゆる被害者側の落ち度として評価される過失相殺においては、別の基準で考えられています。
最高裁は、まず、被害者に事理弁識能力があれば、過失相殺できると判断しています。事理弁識能力とは、道理をわきまえる能力という意味であり、具体的には、5歳ないし6歳で事理弁識能力が備わると判断している裁判例が多くあります。
したがって、未成年者であっても、5歳から6歳くらいですと、その子の行為が過失相殺の対象として問題になりうることになります。
3 まとめ
未成年者が被害者に遭う交通事故の場合にも、過失相殺は問題になりえます。
子どもたちが交通事故に遭わないように、日ごろからのしつけは大変重要ですし、運転する側の注意もとても大事です。
ただ、子供が事故遭われた事例も経験がありますので、お困りの際には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
可動域制限の数値
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
例えば、交通事故によって生じた怪我により、上肢あるいは下肢に可動域制限が残った場合、後遺障害の申請を行うことを検討することになると思います。
2 可動域制限
以下の投稿でもご紹介している通り、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている場合には9級、3/4以下に制限されている場合には12級といった形で、後遺障害等級が認定されます。
しかし、実際に、主治医から後遺障害診断書を作成してもらった結果、診断書内の数値を見ただけでは、よくわからないことがあります。
例えば、角度の計測は5°単位となっていますが、そうでないものもあります。
左右いずれも骨折等の傷害を負った場合には、正常値との比較で検討することもあると思いますが、片方のみの場合には、主治医がどうしてそのような数値になったのか、起点をどうしているのか等も確認しなければならないこともあります。
また、リハビリ前と後でも、数値は違ってくると思います。
以前、以下の投稿でも記載していますので、ご参照ください。
いずれにしても、後遺障害診断書が作成されたら、一度、数字をきちんと確認し、分からない場合には主治医に確認する必要があります。
3 まとめ
以上見たように、上山法律事務所では多くの後遺障害申請に関与し、また、後遺障害の申請に当たり、的確なアドバイスができるよう努力しております。
お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
ギプス固定期間
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
交通事故により骨折等の傷害を負って、ギプス固定されている場合、そうでないケースと何か違いがあるのでしょうか。
2 考え方
通常、交通事故のよってお怪我を負った場合、症状固定とされた時点で、治療費、休業損害、慰謝料といった損害項目に従って損害を算出します。
その際、慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料に区別されます。後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に従って金額を算出します。
入通院慰謝料は、入通院慰謝料は入通院の実日数と治療期間により計算されます。そして、ギプス固定期間は、こちらに影響します。
慰謝料については、3つの基準がありますが、いずれにおいても影響があります
例えば、自賠責基準ではギプスの固定期間は実際に治療行為を受けていなくても、治療行為があったものと評価して慰謝料を算定します。また、任意保険や裁判基準でもギプス固定を通院期間ではなく、入院期間と同視して慰謝料額を算定することがあります。
もっとも、ギプスによる完全固定ではなく、簡易的な固定により日常生活に支障が少ない場合には、固定期間=入院期間という考え方を取らない場合もありますので注意が必要です。
3 まとめ
示談交渉に当たり、慰謝料を算定しますが、ギプス固定期間はきちんと確認する必要があります。
一般に入院期間として評価される期間が長ければ、それだけ金額が大きくなるからです。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
何が差し引きされるのか
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
原則は、相手方の保険会社から回収するのですが、交通事故の被害に遭ったことをきっかけに受け取ったお金は、全て差し引きされるのでしょうか。
専門用語では、損益相殺という言い方をします。
2 具体例
例えば、加害者から見舞金をもらったとします。
これは、加害者からの好意によるものですが、治療費や休業損害といった損害費目の補填のために受け取ったものではないということで、金額次第ではありますが、基本的には損益相殺の対象にはなりません。
死亡事故に遭われて、被害者の方が入っていた生命保険から遺族が死亡保険金をもらった場合はどうでしょうか。これも、それまで支払っていた保険料の対価だということで、損益相殺の対象にはなりません。
一方、相手方の保険会社から支払われた保険金や、労災から受けた給付等は差し引きされます。
何が差し引きされて、何がされないのかについては、判例等で一定程度整理されています。
このコラムでも一度、投稿していますので、ご参照ください。
3 最近あったこと
交通(追突)事故の被害に遭われた方で、人損と物損が生じている案件があります。
人損はまだ治療中ですので、物損の示談交渉が先行していますが、物損の損害額について、保険会社と交渉しています。被害者の方が加入している保険会社も、加害者の方が加入している保険会社も同じ保険会社なのですが、被害者が加入している保険会社の側から、人損に対して見舞金が支払われました。
相手方の保険会社から、それも含めて考えれば、物損も赤字ではない等と主張されています。
そもそも、人損と物損は性質の異なる損害であり、かつ、自分の加入する保険会社から支払われた見舞金が、物損に影響を及ぼすはずがありません。
たまにこのような形でソロバン勘定をしてくることがありますので、注意が必要です。
4 まとめ
示談交渉に当たり、何を差し引きするか、しないかを間違えると金額算定に誤りが生じて大変なことになります。、
的確なアドバイスを致しますので、お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
特殊な交通事故事件
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
しかし、例えば、自動車を走行中に、道路の整備が不良で事故が生じた場合等は、道路管理者である国や自治体を相手にして損害賠償請求をすることになります。
このような場合には、どのような違いがあるのでしょうか。
2 基本的な考え方
まず、責任については、相手方が自動車を運転しているという前提ではないため、自賠法の適用はありません。
そのため、交通事故の被害に遭われた方の方で、相手方(多くは国や自治体)の責任を主張立証する必要があります。
先の例でいえば、国家賠償法2条の問題となり、相手方の管理が、通常有すべき安全性を備えていたかどうかという観点から判断されます。
他方で、交通事故の被害に遭った方の方に過失が無かったかという視点から、過失割合も争点として出てくる可能性はあります。
損害の計算については、基本的な考え方には違いはありません。いわゆる裁判基準あるいは弁護士基準と言われるものに基づいて、典型的な交通事故の場合と同じ計算を行うことになります。
3 請求の相手先
交渉を始めるにあたって、通常の交通事故の場合には、相手方の保険会社が示談代行によって対応していることがほとんどです。
しかし、今回のケースのような場合には、相手方の保険会社が介入することはなく、事故の後、まずは、担当部署(例えば、市道であれば道路管理課)の担当者とやりとりをすることになると思います。あるいは、うまく話が進まなかったり、交通事故の被害者の方で、弁護士に依頼した場合には、相手方の方も弁護士に依頼をして対応することになると思われます。
4 弁護士特約は使えるのか
道路の整備不良といった類型の事故でも、事故証明が発行され、ご自身の加入している弁護士特約が利用できる場合もあります。
現に利用している案件もありますので、保険会社にはしっかりと確認する必要があります。
弁護士特約を使えるのであれば、相手方の担当者とご自身で交渉するストレスから解放され、費用を気にせずに、弁護士に依頼することが可能になります。
5 まとめ
以上見たように、通例の交通事故とは異なる類型の事故の場合もあります。ただ、上山法律事務所ではこのような事故でも対応しております。 お困りの方は、是非、上山法律事務所に
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
既存障害がある場合
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
示談交渉は、損害が確定した後に行うのが一般的であり、お怪我を負われて後遺障害が残存した場合には、後遺障害の申請を行った後に、示談交渉を行うことになります。
例えば、後遺障害の申請を行う際、従前にも交通事故に遭い、後遺障害の認定がなされている場合には、どうなるのでしょうか。
2 基本的な考え方
自賠法施行令は、「既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。」と定めています。
既存障害のある方が、今回の交通事故によって同一部位に後遺障害が残った場合は、既存障害の程度を加重した場合に限って、加重した部分(「加重障害」といいます。)についてのみ自賠責保険金を支払うという意味です。
例えば、既存障害として頚部に14級の障害を負っていた方が、今回の交通事故によって、同様に頚部12級の障害を負った場合、今回の後遺障害12級の自賠責保険金から既存障害の14級の自賠責保険金を差し引いた額が支払われることになります。
しかし、裁判所は、自賠責保険における認定を重視しつつも、独自に、既存障害の有無や程度を踏まえて判断します。
例えば、14級相当の神経症状は、労働能力喪失期間が5年、12級相当の神経症状は同じく10年とされています。
そのため、既存障害が発生した時期から今回の交通事故までに上記期間が経過している場合、既存障害はすでに治癒しているとして、今回の後遺障害への影響はないという主張も十分に成り立ちます。
現に、私どもは、裁判でそのような内容の和解を勝ち取ったこともあります。
一般論として、自賠責よりも裁判所の方が柔軟だと言う意見もあります。
3 まとめ
以上見たように、既存障害のあるケースの場合は、それを前提とするか、あるいは無関係として交渉すべきなのか、非常に判断が難しいケースが多いです。
お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。