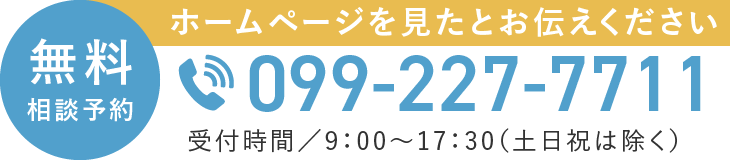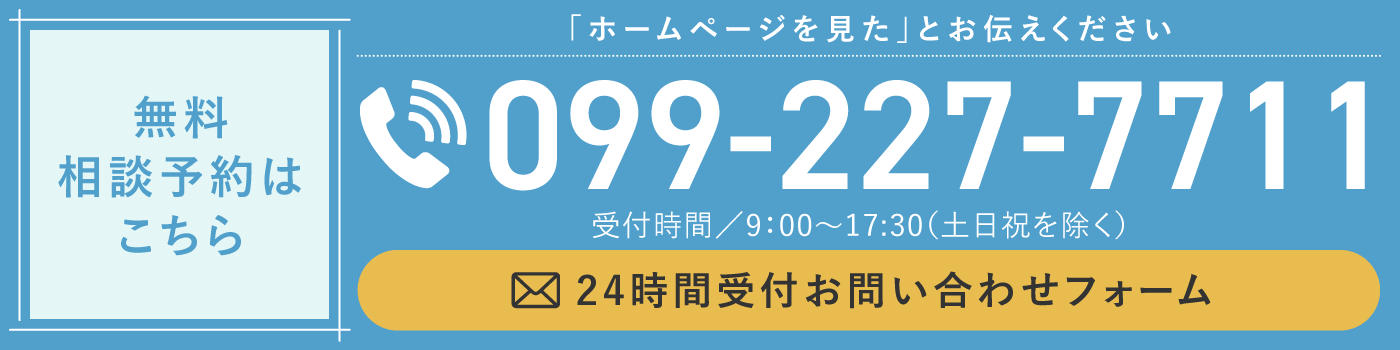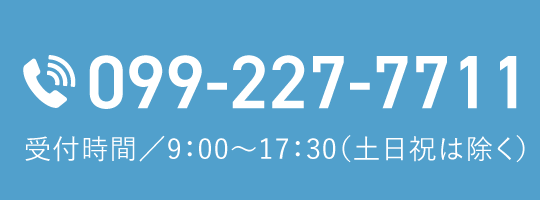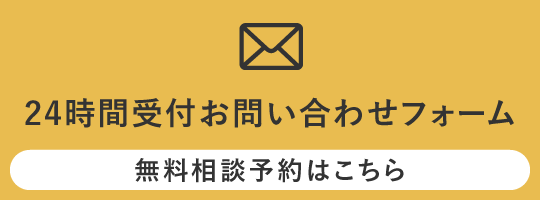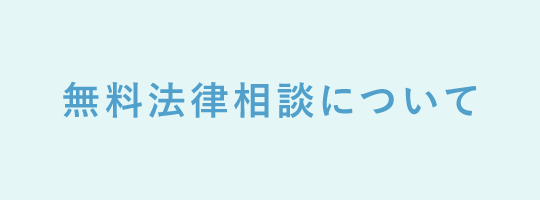Author Archive
後遺障害の申請のための治療継続
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
交通事故によってお怪我を負った場合、後遺障害が残存すれば、後遺障害の認定結果が出てから、後遺障害が残存しなくても、いわゆる症状固定により通院が終了してから、損害を確定させて示談交渉に入ります。
つまり、後遺障害が残存していると考える場合には、その申請を行う必要があります。
2 通院期間はどの程度必要と言われているか
一番典型的なむちうち症状(14級を狙う場合)を例にとってお話をすると、概ね、事故から3か月~6か月くらいが通院期間とされています。
後遺障害の認定のためには、6か月程度の通院期間が必要とされています。
そのため、保険会社が3か月とか、6か月を経過する前に治療費を打ち切ると言ってきた場合には、健康保険に切り替えて、3割を自費で負担して通院を継続する必要があります。
しかし、ここで、問題が生じることがあります。
3 医師側とコミュニケーションがとりにくい場合
主治医が、後遺障害の申請の実務に慣れていなかったり、むちうち診療に好意的でない場合があります。
例えば、保険会社が治療費を打ち切った場合、その時点が症状固定だと考えている医師がいます。症状固定かどうかは、保険会社が決めるのではなく、医学的な立場から医師が判断すべき事柄です。私どもが依頼を受けた案件では、打ち切り後に数か月、自費で治療を継続して後遺障害診断書を作成してもらった際に、保険会社が治療費を打ち切った時点を症状固定だと判断を変えない医師がいました(そうであるなら、何故、継続して治療をするのか分かりませんし、その依頼者の事案では、保険会社が治療費を打ち切った後に、治療方針を変更したという案件でした)。
症状固定の時期により、請求できる治療費や慰謝料の額に影響があります。
もっとひどいケースでは、むちうち診療に好意的でなく、「うちの病院はむちうちは3か月で治療が終了します」等といい、明らかに依頼者が治療の継続を希望しており、保険会社もまだ数か月間、治療を継続しても構わないと言ってるにもかかわらず、医師の方が治療を中止するということもあります。
このような場合には、早めに転院をすることをお勧めします。
結果、その医師に後遺障害診断書の作成をお願いしても、どのような内容になるかは想像がつくからです。
後遺障害診断書の自覚症状の欄を白紙で作成するという医師にも会ったことがあります。他覚的所見欄以外は、単なる患者の主訴であり意味がないという考えのようです。
しかし、むちうちでは、自覚症状の一貫性が重要であることもあります。
4 まとめ
以上見たように、後遺障害の申請に当たり、通院期間・経過は重要です。
しかし、病院の側とのコミュニケーションが取れない場合にもあります。
そのような状況の中でも、何とか最善策を見つけないといけません。
お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
自損自弁について
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
しかし、事故によって生じた損害の内容によっては、自損自弁として処理した方がよい場合もあります。
2 自損自弁
自損自弁とは、交通事故の当事者が双方とも保険を適用せず、自分に発生した損害を自分で負担する解決方法です。
お互いの損害発生額が少額な場合や、自分に発生した損害額と保険を適用した場合の自己負担額が同程度になる場合には自損自弁にすると簡便に解決できます。
たとえば事故によって発生した損害額(車の修理費用)が、相手の分が10万円、こちらの分が5万円だったとします。
このようなケースにおいて、互いに過失割合を計算して対物賠償責任保険を適用して賠償金の払い合いをするのは煩雑です。対物賠償責任保険を使うと、以後、保険料が高くなりますので、経済的な点からも、あえて保険を使わない方が得の場合もあります。
また、過失相殺に争いがあるような場合には、そこで争って紛争解決が長引く可能性もあります。
したがって、お互いの損害が大きくない場合には、自損自弁での解決を検討する意味があります。
ただし、保険を利用した方が得な場合には、保険を利用すべきです。
したがって、自損自弁が得なのかどうか、保険会社に確認した上で、最終的な結論を出すべきです。
3 まとめ
以前から投稿していますが、物損事故は、人損に比べると必ずしも金額が大きく無いケースが多いですが、かといって、簡単に示談できるわけではありません。
自損自弁は、ある意味では過失相殺等の問題を棚上げして解決を目指す点で、少し今まで投稿してきた内容とは視点の異なる解決方法です。
ただ、メリットのある場合もありますので、検討すべき問題であることも事実です。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
後遺障害結果に不満がある場合
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
示談交渉は、損害が確定した後に行うのが一般的であり、お怪我を負われて後遺障害が残存した場合には、後遺障害の申請を行った後に、示談交渉を行うことになります。
後遺障害の申請を行い、納得の行く結果を得られた場合には問題はありませんが、不満のある場合には、不服申し立ての手続きがあります。
2 後遺障害結果に不満な場合の手続き
① 調査事務所に異議申し立てを行う方法
まず、認定結果に不満な場合には、認定結果を出した自賠責調査事務所(以下、「調査事務所」といいます。)に不服申し立てを行うという方法があります。
これは、時効期間内であれば、何度でも可能ですが、認定結果を覆すには、新たな証拠資料等が必要になるのが一般的です。
② 紛争処理機構に調停を申し立てる方法
次に、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」といいます。)に調停の申し立てを行う方法があります。
紛争これは、一度きりしか使うことができないため、この結果にも不満が残った場合には、裁判の中で主張するしかなくなります。
ただ、当事務所の感覚では、補充的に新たな証拠資料等を揃えなくても、認定結果が覆ったケースもあり、調査事務所への異議申し立てよりも認められやすい印象です。
現実問題としては、異議申し立ては何度でも可能ということであっても、複数行うということは無いと思いますので、1度だけ行うということであれば、当事務所では紛争処理機構をおすすめすることも多くあります。
③ 訴訟で争う方法
異議申し立て(①)、調停申し立て(②)以外では、訴訟で争う方法があります。
ただ、裁判所は、調査事務所や紛争処理機構の後遺障害認定結果を、一応、尊重する姿勢でいることが多く、訴訟の中で覆すには相当な努力が必要となります。
3 まとめ
以上見たように、後遺障害結果に不満がある場合に、不服申し立てを行う方法は複数あります。
上山法律事務所では、当初の後遺障害結果を覆した事例も数多く担当しています。
お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
申告外所得について
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
この示談交渉ですが、一般論としては、人損は症状固定になった後に治療費、交通費、休業損害及び入通院慰謝料(後遺障害が残存していれば、逸失利益及び後遺障害慰謝料)といった損害項目を、一括してまとめて支払うよう交渉していくことになります。
これは、これまでの投稿でも述べてきた通りです。
このうち、休業損害や逸失利益の算定において、基礎収入をどのように算定するかという問題があります。
このコラムにおいても、交通事故の被害者が、給与所得者、会社役員、専業主婦(主夫)、個人事業主の場合等について投稿してきました。
今回は、個人事業主の場合について、さらに見ていきます。
2 個人事業主の基礎収入の算定
以下の頁に一般論を記載しています。
「事故の前年度の確定申告書」を利用して基礎収入を算定します。
確定申告書の「所得」金額を基準に365日で割って1日あたりの基礎収入を計算するのが基本的な計算方法です。
では、「確定申告書の内容は、売り上げを過少に申告していたりするので、本当であればもっと所得は大きい」といった主張は認められるのでしょうか。
確定申告書は、自分が税務署に提出したものになるため、これと異なる主張を行うのは自己矛盾であることから、原則としては認められません。
しかし、裁判所は,申告所得を超える実収入額を証明できれば、例外的に申告外所得を認めることがあります。もっとも、申告外所得について厳格な立証が求められているため、なかなか認められていないのが実情です。
申告外所得については、所得を裏付ける預貯金通帳、会計帳簿、伝票類、取引関係書類等から立証することになります。
裁判所の判断は以上の通りですが、裁判になる前の保険会社との示談交渉においては、まず、保険会社は申告外所得の主張は認めないと思われます。全体として、慰謝料の中で少し柔軟に対応するといったようなことはあるかもしれませんが、当事務所で対応してきた感覚としては、裁判所での判断以上に、保険会社は厳しい姿勢であると感じています。
3 まとめ
申告外所得の主張について見てきましたが、実際に、このような状況にいらっしゃる方は、決して少なくないと思います。
ご本人の場合もあれば、死亡事故のご遺族の立場で問題となる場合もあると思います。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
経済的全損について②
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
物損事故に遭い、相手方に、車両の修理費を請求する際に、経済的全損が問題になることがあります。
本サイトでも、以下の投稿をしています。
2 対物超過特約
任意保険会社の商品で、対物超過特約というものがあります
相手方の自動車に時価額を超える修理費用が発生した場合に、差額を補償する自動車保険の特約の一つです。
これまでもお伝えしている通り、物損事故の場合には、過失割合と修理費用が問題となることが多く、特に、経済的全損の事案の場合には、車両時価額や買替諸費用を巡って保険会社と対立することが多いです。
被害者の側からすれば、事故を起こされた上に、手出しで修理費用や買い替え費用を出さなければならないということになり、不満の残る形になりがちです。
この場合に、加害者側がこの特約に入っていると、円滑に解決できる可能性が高まります。
相手方がこの特約に加入していないか、あるいは、自分が事故を起こしてしまった場合に、この特約を使うことができないか、確認されてみてください。
3 まとめ
以前から投稿していますが、物損事故は、人損に比べると必ずしも金額が大きく無いケースが多いですが、かといって、簡単に示談できるわけではありません。
経済的全損は、過失割合と並んで問題になることが多い争点です。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
未成年者の交通事故事件
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
これまで、成人を前提にした記事を多く掲載してきましたが、未成年者の事故の場合には、どうなるのでしょうか。
未成年者の事故の場合の損害の考え方は、本サイトでも既に記載しています。
2 誰が示談交渉を進めるのか
未成年者の場合、行為能力が制限されていますので、親権者が財産管理権限を持つことになります。
そのため、親権者が法定代理人として示談交渉を行うことになります。
日本は親が婚姻中であれば、それぞれの親が共同親権者になりますので、両親が代理人になります。
離婚されている場合には、日本は単独親権ですので(今後、法改正で変わる可能性があります)、離婚の際に定めた片方の親権者が代理人になります。
これは、未成年者が被害者であっても、加害者であっても同様です。
被害者の立場の場合には、親権者の方が相手方の保険会社と交渉するという点が変わるだけで、それ以外の点にはあまり違いはありません。
3 加害者側が未成年の場合
示談交渉を親権者が行うことになるのは前述の通りです。
損害賠償責任を誰が負うのかという点については、検討の必要があります。
加害者が未成年者で資力がないという場合には、親から賠償を求めたいところです。しかし、加害者が未成年だからと言って、必ずしも親の責任を問えるわけではありません。
未成年者が加害者の事故の場合、親の責任を問える可能性があるのは、次の3つです。
①未成年者の子供に責任能力がない場合
②親自身の不法行為責任を問える場合
③親名義の自動車・バイクを運転して事故を起こした場合
①責任能力は、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能と定義されます。何歳になったら備わるのかと言うはっきりとした基準はありませんが、これまでの判例や裁判例を見る限り、大体12歳程度で責任能力があると判断されていることが多いです。
加害者が幼く、責任能力がないと判断される場合は、未成年者に代わって親が責任を負わなければいけません(民法714条1項本文)。
親としての監督義務は、子供の日常生活における行動すべてが対象となりますので、よほど不可抗力によって交通事故が起こったようなケースでなければ責任を免れるのは難しいでしょう。
②親自身に民法709条の責任を問えるケースは、かなり限定的です。
・親による監督が現実に可能だった場合
・親が子の運転する自動車に同乗しており、事故を起こすような危険な運転をしていたのにこれを止めなかったような場合
などが具体例とされています。
③未成年者が、親名義の自動車やオートバイを運転して事故を起こした場合、親は、自賠責法上の「運行供用者」として責任を負う可能性があります。
運行供用者とは、次の2点を満たす場合に認められます。
運行を支配している(コントロールできる)こと
運行の利益を受けていること
4 まとめ
未成年であるお子さんが事故に遭う、あるいは、事故を起こしてしまった場合、自分のこと以上に不安が大きいと思います。そのような中で、保険会社と示談交渉を行うことは、さらに負担が大きいと思います。
上山法律事務所では、このような事例も経験がありますので、お困りの際には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
休業損害を受け取るタイミング
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
この示談交渉ですが、一般論としては、人損は症状固定になった後に治療費、交通費、休業損害及び入通院慰謝料(後遺障害が残存していれば、逸失利益及び後遺障害慰謝料)といった損害項目を、一括してまとめて支払うよう交渉していくことになります。
2 休業損害の請求のタイミング
しかし、被害者の方からすれば、事故によって休業することになれば、有給休暇が利用できれば、減収はないかもしれませんが、そうでない限りには、減収を伴うことが一般的です。
症状固定までの間の生活が厳しく、待つことができないという方もいらっしゃいます。
そのような場合、内払いという形で、相手方保険会社から、毎月、休業損害の一部を支払うよう交渉することもできます。
ただし、当方の過失が大きい場合には、そのような対応を拒絶されることもありますし、内払いの必要性や相当性について争われることがあります。あくまでも任意保険会社による任意の対応にとどまるため、強制はできません。
そのような場合には、自ら、相手方の自賠責保険会社に被害者請求をしたり、交通事故の被害者の方が加入している人身傷害補償保険に対して、対応を求めることもありえます。
休業損害の内払いを受けた分や、自賠責保険ないし人身傷害補償保険から回収したものは、最終的な示談金を算定する際に、既払い分として控除されます。人身傷害補償保険については、当サイトコラムでも投稿していますが、過失割合が問題となるケースでは、まず、過失の部分に充当されることになります。
3 まとめ
交通事故の被害に遭われて、当面の生活にお困りの方は多いと思います。
その際には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
依頼を受けてよいか迷う事件
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の加入する任意保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を回収するよう努めるのが一般的です。
当事務所では、様々な交通事故案件のご依頼を受けて参りました。当事務所の取り扱い業務は、交通事故に限られるものではなく、離婚・相続といった家事事件や、破産・再生等の債務整理事件、労働事件、不動産・建築事件、医療過誤といった、いわゆるマチ弁と言われる弁護士が扱う事件は全て対応しています。
加えて、基本的には、いただいたご依頼については、特段の事情のない限りはお受けしていきたつもりであり、これは交通事故案件も同様です。
しかし、どうしても、依頼を躊躇する、あるいは、お断りしなければならないと判断するケースもあります。
以下では、交通事故案件の場合でご説明します。
2 ご依頼をお受けしにくいケース
以前、本サイトでも投稿しましたので、こちらもご参照ください。
以下で述べるものは、いずれも弁護士特約に加入していないことが前提です。弁護士特約に加入していれば、ご依頼を受けることに基本的には躊躇はありません。
①物損事故で、弁護士特約に加入していないケース
物損事故は、過失割合が問題になるか、経済的全損の時価額が問題になっていることが多いと思いますが、弁護士費用を手出しすることになる場合には、その額と比較検討する必要があると思います。
②依頼者の過失が大きく、挽回できる余地があるか微妙な場合
これについても、ご自身で被害者請求をすることをお勧めしています。自賠責は7割以上の過失の場合しか減額されないため、交通事故の被害者の方に過失が大きい場合には、自賠責に請求するのが一番回収額が大きくなる可能性もあるためです。
③人損の被害者ではあるものの、すでに保険会社から事前提示がなされている金額より、弁護士費用の方が上回るケース
このようなケースも該当します。
後遺障害が問題とならない事故、あるいは、非該当になっている事故の場合には、このようなケースもあり得ます。
ただ、このケースの場合には、後遺障害の非該当の判断に納得ができないということで、異議の申し立てをしたいという相談から対応することもあります。この場合も、新たに主治医から意見書を作成してもらう等の協力が得られるか等、異議申し立ての可能性がどの程度あるかを見極めて検討することになります。
一方、後遺障害が認められているケースの場合には、弁護士費用を手出ししてでも依頼をした方がメリットのある事案も多いと思います。
3 まとめ
以上のとおり、弁護士の側も、せっかくご相談いただいた案件について、依頼を受けるか躊躇する案件があります。
それは、弁護士費用特約に加入しておらず、ご依頼を受けると、経済的には赤字になってメリットが無い場合です。
ただ、弁護士特約に加入していなくても、保険会社との交渉に疲れて、費用が赤字になっても弁護士に依頼したいという方もいます。
相手方が保険会社や弁護士を交渉窓口としておらず、相手方本人が交渉してきて話し合いがうまく進まないため、ストレスを感じて弁護士に依頼したいといったケースもあります。
そのため、ご自身の状況を踏まえて、まずは相談だけでも弁護士にしてみることをお勧めします。
交通事故の被害に遭われて、お困りの方は、上山法律事務所にご連絡ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
近親者の慰謝料について
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行って、適切な賠償金を獲得するよう努めるのが一般的です。
一般論としては、損害賠償請求権は、交通事故の被害者ご本人に発生するものですから、原則としては、ご本人以外は請求できません。
しかし、死亡事故の場合には、交通事故の被害者に発生した損害賠償請求権をご本人から相続した相続人が請求するということになります。
では、例えば、ご本人だけでなく、近親者にも慰謝料が発生したとして、近親者固有の慰謝料を請求することはできるでしょうか。
2 近親者の慰謝料
当然ですが、大切家族が亡くなったり、後遺障害が残ってしまえば、ご家族も大きな精神的苦痛を受けます。
近親者慰謝料とは、近親者固有の慰謝料とも呼ばれるもので、被害者の近親者が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。
「民法」
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法には上記条文があります。
しかし、金額については明確な基準はありません。
死亡慰謝料の計算方法は、自賠責基準と任意保険基準、裁判基準の3つの基準によって異なりますが、遺族固有の慰謝料がもっともわかりやすく認められるのは自賠責基準です。
この場合、慰謝料請求権が認められるのは被害者の父母、配偶者と子どもですが、その金額は請求権者の人数によって異なります。
具体的には、請求権者が1人の場合は550万円となりますし、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円となります。
被害者が扶養していた人(被扶養者)がいる場合、請求権者が1人の場合には750万円、2人の場合には850万円、3人以上の場合には950万円となります。
裁判基準の場合には、「死亡慰謝料」という枠組みの中に遺族固有の慰謝料の金額も組み込まれることになります。
したがって、特段の事情がない限りは、ご本人の死亡慰謝料とは別に近親者慰謝料は発生しないと考えるか、近親者慰謝料の分をご本人の死亡慰謝料の額と調整して算定されている印象です。
3 重度後遺障害が残存した場合
上記民法の条文では、近親者の慰謝料は死亡事故に限られそうにも思えますが、判例では、被害者の方が死亡した時にも比肩しうべき精神上の苦痛を近親者の方が受けたという場合は、近親者からの慰謝料請求が認められます(最高裁判所昭和33年8月5日第三小法廷判決)。
どのような場合に近親者の方に被害者死亡と同等の精神的苦痛が生じたと認められるかですが、後遺障害等級1級・2級などのケースで、近親者慰謝料が認められることがあります。
金額については、死亡のときと同様に基準はありませんが、基本的な考え方は同様であると考えられます。
4 まとめ
交通事故の被害に遭われ、特に、ご家族を亡くされてしまった場合、精神的なショックは大変大きいものと思います。
そのような中で、保険会社と示談交渉を行うことは、さらに負担が大きいと思います。
保険会社の提案が正しいのか、不安もあると思います。
お困りの際には、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
高齢者の死亡慰謝料
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
死亡事故が発生した場合、被害者の相続人は悲しみに暮れる日を送ることになります。四十九日が明けると、相手方の保険会社も示談の提案をしてきます。
事案が事案なだけに、神妙な態度で提案をしてきますが、提案内容を確認しないままに印鑑を押していいのでしょうか。
高齢者の死亡事故の場合、給与収入や年金収入の逸失利益と死亡慰謝料が問題となります。
本日は、このうち、死亡慰謝料についてお話します。
2 死亡慰謝料
死亡慰謝料について、自賠責の基準、任意保険会社の基準、裁判基準と3つの基準があります。某保険会社は、被害者側に弁護士がついていないと、一番低い自賠責の基準で提案をしてきますが、その他の保険会社は、任意保険会社の基準で提案してきます。
自賠責よりは高額ですが、裁判基準よりは低額です。
訴訟に至らずに示談で解決をしようとすると、裁判基準の8~9割のラインでの解決が多い印象ですが、高齢者の場合、さらに注意する必要があります。
まず、死亡慰謝料の裁判基準ですが、以下の通りとされています。
・一家の支柱である場合 2800万円
・母親、配偶者の場合 2500万円
・その他 2000万円~2500万円
一家の支柱の意味については、このコラムでも以前、記載したことがあります。
一家の支柱とは | 鹿児島で交通事故・後遺症でお困りなら無料法律相談対応の弁護士法人かごしま上山法律事務所にお任せください (kagoshima-koutsujiko.com)
以上が、裁判基準です。したがって、これらの金額を前提に、訴訟をしないという前提であれば、どのくらいのラインで示談をするかを検討することになります。
交通事故の被害者の方が高齢の場合、子育てをしている世帯と比較すれば、一家の支柱かどうかについては争われやすくはなります。
また、交通事故の被害者の方に基礎疾患等があり、これも複合的に関連して亡くなってしまったというケースの場合には、素因減額という形で過失相殺的な処理がなされることもあります。
では、そのような事情はなく、交通事故を原因として即死をしてしまったような場合にも、高齢=余命が短いことから慰謝料額は減額されるべきだと主張された場合にはどうでしょうか。
裁判例では、そのような考え方は否定されております。
ただ、保険会社の側が、意図的に低い金額で慰謝料の額を提案してくることがありますので、注意が必要です。
3 まとめ
以上のとおり、高齢者の方の死亡慰謝料について述べてきました。
上山法律事務所では、死亡事故も多く対応してきておりますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。