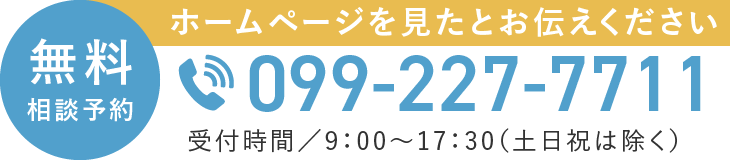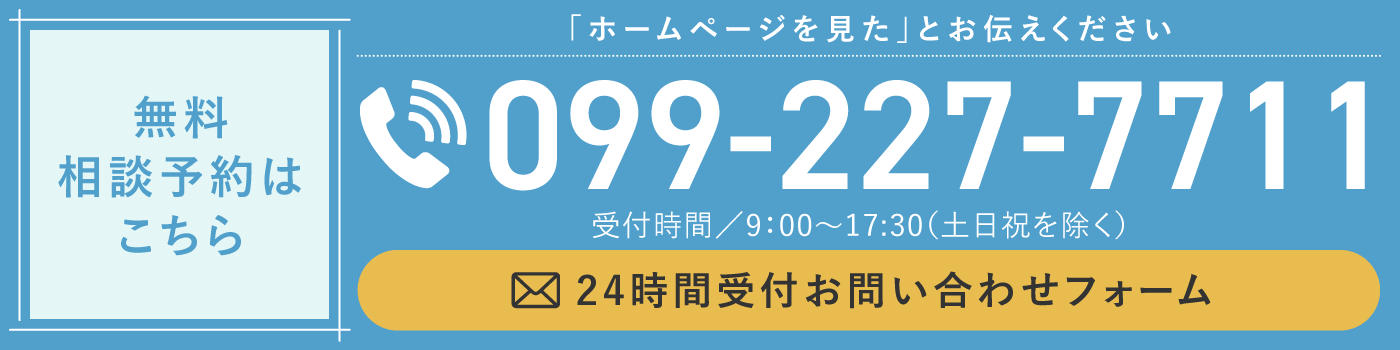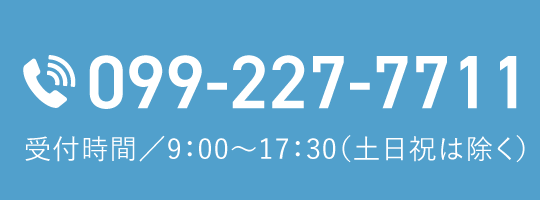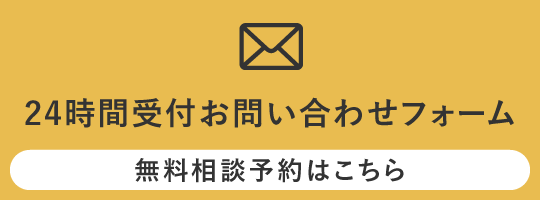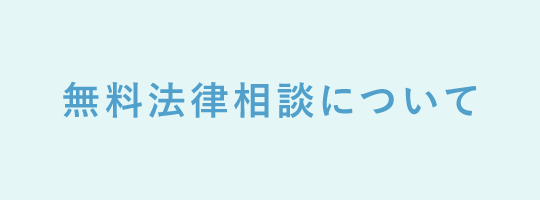Author Archive
交通事故と介護保険
1 はじめに(交通事故と介護保険)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
治療費と健康保険の関係については、前回のコラムで記載した通りです。
では、介護保険はどうなるでしょうか。
2 介護保険の場合
過失割合が0対100の事故の場合に、どうして被害者の側が手続きを取らないといけないのかと思われるかもしれません。
平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
鹿児島市のHPも引用しておきます。
介護保険制度では、介護サービスを利用する際、被保険者は利用料の1割~3割を負担し、残りの9割~7割を保険者(自治体)が介護保険給付として負担しています。
交通事故など第三者(加害者)が原因で介護が必要になった、もしくは要介護状態が悪化した場合は、被保険者(被害者)が介護サービスを利用する際にかかる費用を、原則第三者(加害者)が負担することとなります。
この場合、被保険者の介護サービス利用負担分(1割~3割)については被保険者自身で第三者へ請求し、残りの介護給付分(9割~7割)については被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得して、保険者が過失割合に応じて第三者へ請求することとなります。
つまり、最終的には、加害者が負担することになるのは変わりありません。
3 まとめ
以上のとおり、介護保険を利用する場合に、所定の手続が必要になります。
ただ、過失割合の問題もある場合には、健康保険と同様の問題がありますし、基本的には介護サービスを利用する必要がある場合には、所定の手続をとって利用すべきです。
上山法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
治療費をどうするか
1 はじめに(治療費をどうするか)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
通常、被害者側の過失が大きいといった事情が無い場合には、保険会社が治療費を病院に支払う運用がなされています。
これをそのまま、気にすることなく続けてよいのでしょうか。
2 労災の場合
労災の場合、治療費は労災から出ます。
休業損害について、特別支給金が出ることから、労災に該当する場合には、労災を積極的に利用した方がいいと思います(これは、損益相殺として差し引きされません)。
では、労災以外の場合にはどうでしょうか。
基本的には、被害者側に過失がない場合には、特に気にする必要がないかなと思います。
ただし、自賠責保険の傷害部分の上限金額は120万円であり、加害者側の保険会社は、治療費等含めて被害者に支払う損害賠償金の総額が120万円を超えそうになると、保険会社の自腹分が出ることを避けるために、治療の打ち切りや治療費の支払いの打ち切りを宣告することがあります。
通院が頻回で、120万円の枠内を治療費が多く占めてしまうような場合、結果として、慰謝料が圧縮される格好になる可能性もあります。
健康保険に切り替えれば、結果として慰謝料を確保した示談がスムーズになる可能性はあります。
また、被害者側に過失がある場合はどうでしょうか。
被害者にも過失がある場合には、被害者も、自身の過失の限度で治療費を負担することになります。
健康保険を利用しないことにより治療費が膨れ上がれば、被害者の負担も大きくなります。
例えば、被害者の全損害が1000万円、過失割合が加害者80%、被害者が20%とすれば、被害者が受け取れる損害額は800万円になります。
このとき被害者が健康保険を使わず自由診療を受け、その治療費が100万円とすれば、被害者が受け取れる800万円を治療費の支払に充てると、被害者の手元には700万円が残ります。
しかし、健康保険を利用すれば、自己負担分は3割の30万円ですので、800万円―30万円=770万円が被害者の手元に残ることになります。
したがって、被害者にも過失がある場合には、健康保険を利用した方が被害者に有利になるのです。
3 まとめ
以上のとおり、治療を継続する過程でも気を付けないといけないことがあります。
上山法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
弁護士特約についてのおさらい
1 はじめに(弁護士特約についてのおさらい)
弁護士特約は、交通事故の被害者にとって、弁護士への依頼のハードルを下げるとても大事な商品です。
これまでも、当サイトのコラムでも、投稿しています。
この弁護士特約ですが、弁護士報酬の上限は300万円となっています。大半はこの範囲内で賄えるであろうと思います。当事務所で弁護士特約を超える案件は記憶にありません。
今回は、たまに聞く誤解について、以下の通り正しい知識を持っていただきたく投稿します。
2 よくある誤解
(1)ご自身が自動車保険に加入していなかったり、加入している自動車保険に弁護士特約をかけていない場合には使えない?
これはおそらく一番多い誤解です。
以前の投稿を引用しますので、よくご確認いただきたいのですが、配偶者や同居の親族、別居していても未婚の子の場合には、ご自身が入っていなくても家族の保険の特約を使えます。
(2)弁護士特約を使っても手出しがでる?
弁護士報酬が300万円を超える事案の場合や、人身傷害補償保険、労災等の相手方保険会社の対人賠償から回収した金員以外については、弁護士特約による弁護士報酬の支払いの対象外になります。
別途、依頼した事務所との委任契約の内容によっては、弁護士報酬を支払う必要がある可能性があります。
ただ、相手方保険会社から支払われたお金のうち、300万円を超える部分に報酬が発生するものと誤解されている方もいますが、これは違います。
例えば、相手方の保険会社から500万円の賠償金が支払われた場合に、500万円―300万円の差額200万円について、何らかの弁護士報酬が発生すると誤解されているケースです。
弁護士特約は、ご自身の加入する保険会社から支給されるものです。
例えば、500万円を回収した場合、日本弁護士連合会の旧報酬基準にあてはめると、
着手金 34万円(500万円×5%+9万円)+消費税
報酬 68万円(500万円×10%+18万円)+消費税
となります。
合計は102万円+消費税になりますから、300万円以内ですので、弁護士費用は特約で全て支払われます。
3 まとめ
上山法律事務所では、弁護士特約加入の有無を問わず、交通事故の相談は無料としていますので、まずはお気軽にご相談ください。私どもの方で弁護士特約の利用の可否を調査することも可能です。
お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
逸失利益についてのおさらい③ 未就労年少者の死亡逸失利益の場合
1 はじめに(逸失利益についてのおさらい② 未就労年少者の場合)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
交通事故の被害に遭われた方が亡くなってしまったり、後遺障害が残存したりした場合、逸失利益が問題となります。
逸失利益とは、その被害者において事故がなければ得られたはずの将来の利益のことをいいます。 逸失利益は、基本的には将来の収入を現在に割り戻して算出します。
これまで、本サイトのページやコラムでも、以下の通り、たくさん投稿してきています。
今回はは、未就労年少者の逸失利益についておさらいしたいと思います。
【後遺障害の逸失利益】
【高齢者の逸失利益(年金)について】
【逸失利益のおさらい①】
【逸失利益のおさらい②】
2 未就労年少者の死亡逸失利益
死亡逸失利益は、原則として、「基礎収入」×「就労可能年数に対するライプニッツ係数」×「1-生活費控除率」で計算されます。
未就労年少者の場合、「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」が、死亡時から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数から、死亡時から就労開始までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引いたライプニッツ係数を乗じて算定します。
この点は、後遺障害逸失利益とほとんど同じ考え方です。
「基礎収入」について、注意事項は、前回、後遺障害逸失利益の際にお伝えしました通りです。
また、大学生等又は大学等への進学の蓋然性が認められる場合、大学卒等の平均賃金を基礎とすることもあります。しかし、高校卒であれば18歳からになりますが、大学卒だと22歳からになります。そのため、大学卒の方が、平均賃金が高いから有利になるかというと、単純にそうはならず、しっかりとシュミレーションをしてから検討すべきです。
「生活費控除率」にちて、概ね、年少女子(基礎収入が全労働者の平均賃金の場合)45%程度、女性30%、男性50%とされています。一般に、男性の年少者よりも女性の年少者の方が低くなります。なお、女性の年少者の基礎収入を全労働者の平均賃金とする場合には、女性の平均賃金とする場合よりも生活費控除率が高くなる傾向があります。
3 まとめ
以上のとおり、未就労年少者の死亡の逸失利益について述べてきました。
後遺障害の逸失利益と同様に、基礎収入について、職種別や大学卒検討すべきかは、よく考える必要があります。計算もきちんと専門家に行ってもらい、正確な金額を算出してもらった方が安心です。
上山法律事務所では、死亡事故事案も多く対応していますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
逸失利益についてのおさらい② 未就労年少者の後遺障害逸失利益の場合
1 はじめに(逸失利益についてのおさらい② 未就労年少者の場合)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
交通事故の被害に遭われた方が亡くなってしまったり、後遺障害が残存したりした場合、逸失利益が問題となります。
逸失利益とは、その被害者において事故がなければ得られたはずの将来の利益のことをいいます。 逸失利益は、基本的には将来の収入を現在に割り戻して算出します。
これまで、本サイトのページやコラムでも、以下の通り、たくさん投稿してきています。
今回はは、未就労年少者の逸失利益についておさらいしたいと思います。
【後遺障害の逸失利益】
【高齢者の逸失利益(年金)について】
【逸失利益のおさらい①】
2 未就労年少者の後遺障害逸失利益
後遺障害の逸失利益は、原則として、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。
未就労年少者の場合、「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」が、症状固定時から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数から、症状固定時から就労開始までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引いたライプニッツ係数を乗じて算定します。
「基礎収入」について、 年少男子の場合、原則として、男性労働者の全年齢平均賃金(以下「平均賃金」といいます)を基礎とします。
年少女子の場合、男女を合わせた全労働者(以下「全労働者」といいます)の平均賃金を基礎とします。
医学部、看護学部、薬学部等で専門教育を受けている学生については、特定の職業に就く蓋然性が認められる場合、職種別の平均賃金を基礎とします。
また、大学生等又は大学等への進学の蓋然性が認められる場合、大学卒等の平均賃金を基礎とすることもあります。
しかし、これには注意が必要です。年少者の基礎収入を大学卒の平均賃金とした場合には、就労開始の時点が変わります。高校卒であれば18歳からになりますが、大学卒だと22歳からになります。そのため、大学卒の方が、平均賃金が高いから有利になるかというと、単純にそうではありません。
この点は間違いが起きやすいので、しっかりとシュミレーションをしてから検討すべきです。
3 まとめ
以上のとおり、未就労年少者の後遺障害の逸失利益について述べてきました。
基礎収入について、職種別や大学卒で検討すべきかは、よく考える必要があります。計算もきちんと専門家に行ってもらい、正確な金額を算出してもらった方が安心です。
上山法律事務所では、後遺障害事案も多く対応していますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
初回相談~交通事故の場合~
1 はじめに(初回相談~交通事故の場合~)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
今回は、弁護士が受ける初回相談について、記載します。
2 相談のタイミング
相談のタイミングは様々です。
例えば、以下のパターンがあります。
①事故直後
②保険会社から打ち切りを言われたタイミング後遺障害申請を行うタイミング
③一度、後遺障害が認定されたタイミング
④保険会社から示談金の提示があったタイミング
私ども上山法律事務所では、①のタイミングを推奨していますが、この場合には、事故から間がないため資料はあまり手元になく、保険会社の手元にもないということも多いです。ただ、刑事事件の被害者としての対応のアドバイスや、今後の病院との付き合い方まで、多角的にアドバイスできます。
②~⑤のタイミングの場合には、事故証明、診断書、診療報酬明細書、あるいは、物損の修理見積書等も保険会社の手元にあることが多いです。
初回相談をお急ぎの場合には、ひとまず、交通事故の被害者の方の手元にあるもの全てをご持参いただき、正式にご依頼をいただいたら、私どもの方で、保険会社から資料の取付を行うという段取りをします。
初回相談まで日にちがある場合には、交通事故の被害者の方ご自身で、相手方の保険会社の担当者に連絡してもらい、上記資料の取付を行っていただいて、それをご持参いただき、相談を実施するという段取りをします(もちろん、保険会社にどのように伝えたらよいかは、こちらからお知らせしております)。
後者の段取りの方が、初回相談が充実することは事実です。そのため、可能であれば、資料の取付をしていただいてから、相談に来ていただけるとありがたいなと思っています。
特に、②③の場合には、今後の治療を継続するかどうかといった判断、あるいは、これまでの診療経過から、後遺障害が認定される可能性があるか、可能性があるとして、主治医の先生にどのように後遺障害診断書を作成してもらうかといった判断をするためには、これまでの資料が不可欠です。
④についても、異議申立てを行うかどうかの判断のためには、そもそもどのような理由で等級認定がなされたのか、異議申し立てのためにはどこを補充するかといった判断のために、上記資料が不可欠ですし、⑤についても、これまでの診療経過を踏まえないと、慰謝料の算定等ができません。
3 まとめ
以上のとおり、初回相談のタイミングは様々ですが、上山法律事務所では、なるべく早い時期の相談を推奨しています。
その際、できれば、保険会社から資料を取り付けて相談にお越しいただけると助かります(もちろん、ご依頼をいただいた後で、こちらから取り付けることも可能です)。
交通事故の被害に遭われたてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
逸失利益についてのおさらい①
1 はじめに(逸失利益についてのおさらい)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
交通事故の被害に遭われた方が亡くなってしまったり、後遺障害が残存したりした場合、逸失利益が問題となります。
逸失利益とは、その被害者において事故がなければ得られたはずの将来の利益のことをいいます。 逸失利益は、基本的には将来の収入を現在に割り戻して算出します。
これまで、本サイトのページやコラムでもたくさん投稿してきています。
今回は、後遺障害の逸失利益についておさらいしたいと思います。
【後遺障害の逸失利益】
【高齢者の逸失利益(年金)について】
2 後遺障害の逸失利益
後遺障害の逸失利益は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。
詳しくは、上記【後遺障害の逸失利益】のページをご参照ください。
最近の事例で、被害者が高齢者の場合で、症状固定から「67歳までの期間」と「平均余命の2分の1」を比較し、後者の方が長いという事案が続きました。
両方を比較しなければ、金額が少ない計算で提示することになり、ミスが生じてしまいます。
当初、前者での計算だけを行っており、改めて、依頼者の方と相談する際に両方の計算をしたところ、後者の方が長いことが分かったという、まさにヒヤリハットな状況でした。
実際に両社を比較すると、200万円くらいの差が生じていました。
単純ミスが生じないように、肝に銘じないといけません。
3 まとめ
以上のとおり、後遺障害の逸失利益について述べてきました。
一見すると、67歳までの方が、平均余命の2分の1より長そうだけど、実は計算すると、後者の方が長かったというケースがありえます。
計算もきちんと専門家に行ってもらい、正確な金額を算出してもらった方が安心です。
上山法律事務所では、後遺障害事案も多く対応していますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
高次脳機能障害の後遺障害申請②
1 はじめに(高次脳機能障害の後遺障害申請)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
事故に遭われた方が、高次脳機能障害と診断された場合、症状は重く、通院期間も長くなります。
このホームページにおいても、高次脳機能障害の一般論については、以下に記載しています。
また、コラムの中でも、以下のページに当事務所で扱った事例を掲載しています。
今回のコラムでは、最近取り扱った事例をご報告致します。
2 後遺障害申請に必要な書類
高次脳機能障害の申請に必要な書類のうちの一つとして、日常生活状況報告書というものがあります。
これは、基本的には同居している家族に書いてもらうことが多いと思います。
交通事故の被害者の方の事故からの状況変化を、一番に把握していると思われるからです。
では、一人暮らしの方の場合や、ご家族に協力を求めることができない方の場合は、どうなるでしょうか。
その場合には、一番、接触頻度の高い方にお願いすることになると思います。
例えば、事故後に仕事復帰している方の場合には、職場の同僚や上司等にお願いすることになると思います。
同居している家族の方に比べると、分からない部分も出てきてしまうかもしれませんが、可能な限り詳細に記載をお願いすべきです。
症状の変化については、主治医の意見書もありますので、後遺障害認定に当たっては、それらも総合的に評価されることになります。
3 まとめ
上山法律事務所では、高次脳機能障害の取り扱い実績も多数あります。
高次脳機能障害その他後遺障害の等級申請等でお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
相手方が無保険の場合②
1 はじめに(相手方が無保険の場合)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
本来、民法の世界では、損害賠償請求をしようとする方が、相手に過失があったことを証明する必要があります。
しかし、自動車損害賠償保障法(以下、自賠法といいます)が適用される場合、加害者の側で過失が無かったことを証明する必要があります。
これは被害者の救済に寄与しますが、一点、重要な点があります。
運行供用者責任です。
2 運行供用者責任
「運行供用者」とは、自動車の運行を支配し、運行による利益を享受する者をいいます。すなわち、自動車を自ら運転し、自動車を直接支配する場合のみならず、他人に運転させて、他人の運転を通じて自動車を間接的に支配する場合を含みます。
これは、加害運転者や運転車両が任意保険に加入していれば、結局は保険会社が対人賠償で損害賠償金を支払うことになるので、結論としては大きな違いはないかもしれません。
しかし、相手が無保険だった場合には、例えば、運転者だけでなく、当該車両を貸与した者にも責任を問うことが可能になります。
相手方が任意保険に加入していないケースというのは、決して珍しくありません。
期間が切れていたり保険料が引き落とされていないのを失念していたり、あるいは金銭的な余裕がなくて加入していなかったりという事情が考えられます。
少なくとも後者の場合には、被害者の方が損害賠償金を回収できるかという点にリスクが生じますので、少しでも、責任を負う者=請求先が増えることで、リスクを減らせないかを検討することが重要です。
ご自身の加入する人身傷害補償保険があれば、この点のリスクをカバーできますが、歩行者や原付等であったり、家族も含めてご自身の保険に加入していない場合には、これを利用することもできません。
3 まとめ
上山法律事務所では、相手方が無保険の事故も取り扱い実績があります。
お困り方は、是非一度、上山法律事務所にご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。
バスやタクシーの中での事故
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
前回は、相手方車両がバスのときのことを記載しました。想定していたのは、バス対自家用車や、バス対歩行者でした。
2 バスやタクシーの中での事故について
では、バスの乗客が、バスの運転手の過失によって怪我をした場合にはどうでしょうか。
結論としては、このような場合もバス会社を相手に請求できることは変わりません。
タクシーに乗車中に運転手の過失により事故が発生した場合等も、同様の状況になります。
基本的には、バスやタクシー会社の加入する保険会社が対人賠償という形で、示談代行をしてくると思います。
損害の算出の方法も、基本は変わらないと思います。
その他の点は、前回の投稿をご覧ください。
3 まとめ
以上見たように、基本的には、バスやタクシーが相手でも、示談交渉の手順や考え方に大きな違いはありません。
お困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。
平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。